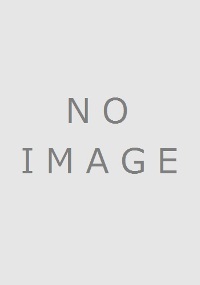跨文化学術行脚
出版社: 花鳥社
- デジタルネイティブ世代が経験していない、インターネット前夜の感触。ウェブ通信網にまだ地球全体が覆われていない時代の、世界各地の息遣い――多分野に跨がる学術対話の最前線ともいえる現場証言や感慨を集約した、半生にわたる海外学会行脚の記録。
未来の研究者たちへ! - 序文―—若い読者への伝言
第Ⅰ部 留学時代の追憶
01 『Actes』誌のことなど
02 ピエール・ブルデュー著『話すということ』
03 『話すということ』について話すということはどういうことか
04 ピエール・ブルデュー『世界の悲惨』について
05 ブルデュー『マネ、ひとつの象徴革命』余滴
06 強制退去の顛末
第Ⅱ部 海外学会参加報告より
01 言葉と映像研究第一回国際会議報告
02 認識と相互理解
03 ヨーロッパとアラビアの学際交流
参考 マルタ島の第二回ユーロ・アラブ夏期大学に招かれて
04 日本再考ヴェネチア会議に招かれて
05 朝のお勤め
06 「東洋のしるし、西洋のしるし」に出席して
07 広州駅頭に日は暮れて
08 現代諸宗教の相互人類学に参加して
09 「跨文化的意志疎通と国際理解」に参加して
10 橋と壁とをめぐって
11 「壁なき大学」L’Université sans mur 発足始末
12 現代言語文学国際協会(FILLM)一九回大会(ブラジリア)参加記録
13 ハマメット国際文化センター「聖なるものの表象、その逆説」に参加して
14 インター・アート・スタディーズ学会参加報告
15 “ポスト・コロニアル”の周辺
16 コペンハーゲンの古本屋
17 欧州学会巡業どさまわりの記
18 在外研修の報告――ニューヨーク・コロンビア大学、パリ東洋語学校
19 郷愁の旅路――日本と「西洋」を往還する文学的巡礼
20 第十四回国際研究集会「文化の越境」
21 エジプト調査の報告
22 世界の段差に肌を晒す――アフリカ・マリの旅から
第Ⅲ部 海外での教鞭経験・余滴
01 ドイツ文化状況瞥見
02 ハイデルベルクの古本屋
03 「出来事」ザールブリュッケンへ 亡命者たちとの、ゆきずりの会話
04 「北京報告」北京外国語大学
05 北京外国語大学日本研究中心 二〇〇一年度秋学期派遣教授離任挨拶
06 サラマンカ日本研究事情「ご報告」
07 哲学的な普遍性を授けられた折り紙
08 二十一世紀の日本武道の行方――異文化交流の立場から
09 いま「アジア」を観る 複数言語競合のアジア
10 岡倉天心とインド
11 ワシントンD.C.の古本屋
12 マルセル・グリオールとアマドゥ・ハムパテ・バとのあいだ
13 ストラスブール大学・国際学会「日本と欧州の出会い」から
14 欧州・伯国聖州行状備忘録
第Ⅳ部 留学生育成・文化交流事業への提言
01 [特別インタビュー]未来の世界像を「海賊史観」から探る
02 [インタビュー]海賊史観から世界を見る
03 基金のネットワークが未来を築く
04 [コメント]インドにおける日本文学・文化研究の将来に寄せて
第Ⅴ部 招聘事業周辺での偶発の出会いから
01 延辺調査備忘録
02 ベンガル点描――インドにおける大観・春草の足跡とムクル・ディーの周辺
03 サンクト・ペテルブルグでの出会い
04 韓国に比較文学の「辺境=最前線」Frontierを踏査する
05 生き残るということ
06 布と織物の現代的可能性
07 ブリコラージュとスクラプチャー
08 市民の都市生活と博物館――ハーレムのテイラー博物館とその周辺
09 裏側からみた日本――サン・パウロで日本を論じる
10 フランスの研究所と大学システム
11 時のうつわ、魂のうつし――二〇一五年一月二四日
12 「日本の凧」国際シンポジウムに参加して
13 Modern Japan in Comparative Imagination, An Interdisciplinary Conference at Durham University, 9-10 May, 2019 参加報告
14 Unique or Universal? 日本とその世界文明への貢献
15 海洋と環太平洋・島嶼を視野におさめた次世代の研究計画に向けて
第Ⅵ部 【現代の言葉】時評・新聞連載ほか 抜粋
01 「手触り」が魂を訓育する『読売新聞朝刊』
02 [工藝の潜在力]欲求喚起の仕掛け必要『京都新聞朝刊』
03 【現代のことば】1 数値にならない価値の復権――金融と経済の現在を考える 『京都新聞夕刊』
04 【現代のことば】2 ヤマモモの実が坂道に 『京都新聞・夕刊』
05 【現代のことば】3 希望の色は何色か 『京都新聞夕刊』
06 【現代のことば】4 私腹の財から公共の財へ 『京都新聞夕刊』
07 【現代のことば】5 高等教育・研究の危機的現状 『京都新聞夕刊』
08 【現代のことば】6 大学の再定義――巣立ちの礎として 『京都新聞夕刊』
09 【現代のことば】7 妖怪と戯れて――学的想像力の現在 『京都新聞夕刊』
第Ⅶ部 離職を迎えて 国際日本文化研究の課題と反省
01 国際日本文化研究センターにおける共同研究を考える
02 二〇年後の文化科学研究科人材養成にむけて――人間文化研究機構での検討会から
03 インターネット双方向的同窓会 NichibunkenInteractiveAlumniNetwork 創設にむけての個人的提言
04 「国際日本研究」の現状と課題――機関としての日文研の運営との関連で
05 日文研次世代の国際共同研究・研究協力への模索
06 「パンデミック」は何の予兆なのか? ――身近な「悔い改め」への舵取りのために
07 【退任のごあいさつ】辞職の辞――「辞職」する者が、職場に伝言を遺して行く、というのは、妙ですね
跋文・跋文補遺
【巻末付録】
主要な「跨文化」学術講演会・学会発表および海外渡航歴
索引