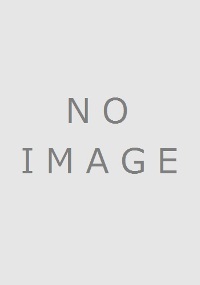中世神仏の文芸と儀礼
出版社: 文学通信
- 宗教言説と文芸との交渉のありさま、そしてその土壌となった儀礼空間をどう読み解くか。
仏教儀礼の場で生成されるテキスト類の特質と、その思想的・文化的背景を明らかにする。
本書は『神道集』および『辰菩薩口伝』『龍王講式』等の儀礼関連資料を中心に、中世宗教文芸の諸相と、その思想的基盤となる信仰や学問体系、成立環境について考える。
儀礼の言説から生じた文芸と、それを論理的に支えた思想との相関性を探るべく、第Ⅰ部「『神道集』の言説と思想」では、法会の言説に連なる『神道集』の本文表現を確認しながら、『神道集』を構築する知識の基層を分析。これによって『神道集』の根底に広がる教理・教説や神祇信仰、また注釈世界の様相を詳らかにし、『神道集』が重層的な営みの上に成り立つことを示す。
つづいて第Ⅱ部「真言宗寺院の儀礼と文芸」では、真言宗寺院に所蔵される儀礼関連の文献資料を検討する。とくに称名寺聖教の吒枳尼天関連資料や、天野山金剛寺蔵の『龍王講式』の分析を通して、儀礼関連資料の背景となる教説や学問活動の様態を探る。 - 序 章
一 本研究の方法
二 各章の梗概
第Ⅰ部 『神道集』の言説と思想
第一章 『神道集』研究史
一 本地垂迹説と『神道集』
二 『神道集』の成立と諸本
三 『神道集』研究の展開
第二章 『神道集』の本文表現と仏教儀礼
はじめに
一 本地説の形式と修辞
二 本地説の文言と法会資料
三 『神道集』の文章形成
おわりに
第三章 『神道集』の神祇観と実者
はじめに
一 神の分類「権者」と「実者」
二 実者神と「実業」
三 「権化実類」をめぐる中世の言説
四 『神道集』の三分類
おわりに
第四章 『神道集』「諏方縁起」の女神と禁忌
はじめに
一 南北朝期の「家」の問題
二 『神道集』の夫婦
三 「諏方縁起」の主題
四 春日姫と荒膚 / おわりに
第五章 『神道集』「白山権現事」の王子たち
はじめに
一 「五人王子」の本地説
二 白山信仰と禅定道
三 白山と五台山
おわりに
第六章 『神道集』の「鹿嶋縁起」と注釈
はじめに
一 『神道集』の「鹿嶋縁起」
二 鹿嶋神と天津児屋根
三 神宮寺と十一面観音
四 金鷲・銀鷲と日本紀注
五 『神道集』と東国の諸注釈
おわりに
第Ⅱ部 真言宗寺院の文芸と儀礼
第一章 『神道集』の辰狐王菩薩曼荼羅
はじめに
一 稲荷神の本地説
二 辰狐王と文殊菩薩(一)外用の徳
三 辰狐王と文殊菩薩(二)内証の功
四 対句表現と儀礼テキスト
五 眷属たちと本尊図像
六 『神道集』の現世と後生
おわりに
第二章 『辰菩薩口伝』と中世仮託文献
はじめに
一 「安然口決」と円密一致の曼荼羅
二 『法華経』と密教
三 「智証大師口決」と八分肉団
四 「真言法華の肝心」としての吒枳尼天
五 吒枳尼天をめぐる天台系所説
おわりに
第三章 『辰菩薩口伝上口決』と法華曼荼羅
はじめに
一 吒枳尼天の口決と円密の一致
二 並座する二仏と五大法性の宝塔
三 毘沙門天の宝塔と身心
四 吒枳尼天と即位灌頂
おわりに
第四章 『龍王講式』の式文世界
はじめに
一 天野山金剛寺蔵『龍王講式』における典籍利用
二 『釈摩訶衍論』の龍と宝珠
三 請雨経法と龍宮世界
四 神泉苑の石座と「最極秘事」
おわりに
結 語
初出一覧
あとがき
索引(Ⅰ書名・Ⅱ人名・Ⅲ神仏名・Ⅳ事項・地名)