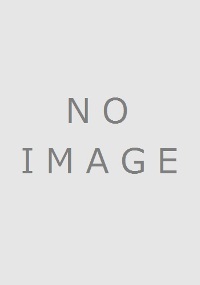障害という経験を理解する
出版社: 北大路書房
- 障害経験は社会的障壁や他者の態度などに大きな影響を受ける。社会と人にまつわる多様な切り口から障害経験の理解を試みる。
- 私たちはみな人生のあらゆる場面で何らかの障害を負う可能性がある。その障害という経験は,個人の心身機能や資質よりも,社会的障壁や他者の態度・行動といった状況要因に大きな影響を受けて形づくられる。バイアス,ジェンダー,老化,職場,家族,政策等,社会と人にまつわる多様な切り口から障害経験の理解を試みる。
- 監訳者まえがき
はじめに
序文と謝辞
第1章 障害という経験を理解する――社会心理学・リハビリテーション心理学の視点から
1. 確立された研究分野
2. 主流のトピック
3. 新たな問題
4. 不公正,アドボカシー,社会政策の問題
5. 障害に対する社会心理学的視点
第Ⅰ部 確立された研究分野
第2章 障害のスティグマ――原因,結果,変化のための方略
1. 知覚者の視点:障害に関するスティグマはどのように持続するのか
2. 障害者の視点:障害に関するスティグマはどのように経験されるのか
3. 障害に関するスティグマをどのように減らすのか:可能性と落とし穴
4. おわりに
第3章 障害を判断する――社会心理学とリハビリテーション心理学で見出されたバイアス
1. 社会心理学的バイアス
2. リハビリテーション心理学で研究されているバイアス
3. おわりに
第4章 障害者への「無能だが温かい」ステレオタイプが選択的共感をもたらす――認知・感情・神経における固有の特徴
1. 両面価値的ステレオタイプが障害のある外集団への選択的共感を支える
2. 知覚された責任が障害者への共感を調整する
3. 障害者という外集団への共感と相関する神経活動
4. 内集団と外集団の共感における神経的差異
5. おわりに
第5章 障害者に対する偏見を減らす
1. 偏見を減らすための様々な戦略
2. 職場における偏見低減戦略
3. おわりに
第6章 リハビリテーション心理学の基礎原理と社会心理学の理論――グローバルヘルスにおける交差とその応用
1. リハビリテーション心理学の基礎原理
2. おわりに
第7章 障害へのコーピングと適応に影響を与える心理・社会的要因
1. コーピングと適応のモデル
2. コーピングと適応に関連する研究
3. おわりに
第Ⅱ部 主流のトピック
第8章 障害のある女性たち――社会的な挑戦の中で女性らしさを保つために
1. 障害のある女性へのステレオタイプ
2. セクシュアリティと交際関係
3. セクシュアリティ
4. 虐待
5. 役割の転換と自己意識の保持
6. おわりに
第9章 ⽂化,⼈種,障害
1. 定義
2. ⼈種・⺠族的マイノリティグループにおける障害を有する割合
3. 理論的枠組み
4. 障害における⽂化的側⾯
5. 提⾔と結び
第10章 性格と障害――多様なより糸から織り成される学術的タペストリー
1. 最初の糸:学術的理論,臨床的ニーズ
2. 社会的認知の多彩なより糸
3. タペストリーの全景:すべてが織り成された先に
4. パーソナリティに関する理解の今後の方向性と深化
第11章 ソーシャルサポート,慢性疾患,障害
1. ソーシャルサポート
2. 構造的サポート
3. 機能的サポート
4. おわりに
第12章 老化と老化に関連した障害
1. 老化の構成要素
2. エイジングパラドックスと後天性障害
3. 高齢者における過剰な障害
4. 老化による障害の社会的要因
5. おわりに
第Ⅲ部 新たな問題
第13章 職場における障害
1. 障害の定義とカテゴリー化
2. 労働力における障害の歴史
3. 障害者を雇用するメリット
4. 労働力における障害者の課題
5. よりインクルーシブな職場環境の構築
6. おわりに
第14章 障害者に対する潜在的態度と行動
1. 障害に関するスティグマ
2. 態度の二重過程
3. 障害者に対する二重の態度と行動
4. 研究からの示唆と今後の方向性
5. おわりに
第15章 障害者の自己カテゴリー化,アイデンティティ,自尊心の研究
1. 社会的アイデンティティ理論
2. 主な障害者アイデンティティの構成要素
3. 主要な研究成果
第16章 家族,子育て,障害
1. 障害児と共にある家族
2. 成人における関係性
3. 障害のある親
4. おわりに
第17章 ポジティブ心理学と障害
1. 問いの3 水準
2. ポジティブ心理学的介入
3. おわりに:リハビリテーション心理学と障害研究に対する示唆
第18章 自己決定の社会心理学と障害
1. 自己決定
2. 自己決定と障害
3. おわりに
第19章 レジリエンスと障害――個人内要因,対人的要因,社会環境要因
1. 個人内要因
2. 対人的要因
3. 社会環境
4. おわりに
第Ⅳ部 不公正,アドボカシー,社会政策の問題
第20章 不公正評価と障害
1. 健康状態を理由とした不公正評価の定義とその位置付け
2. 現状におけるエビデンス
3. 今後の方向性
4. おわりに
第21章 新時代のための障害のアドボカシー ――社会心理学の活用と変化のための社会政治学的アプローチ
1. 障害のアドボカシー:過去そして現在
2. 障害のアドボカシー研究が検討する課題
3. おわりに
第22章 社会政策と障害――リハビリテーション心理学実践,研究,そして教育への影響
1. 障害に関する公共政策の概要
2. リハビリテーション心理学の実践および教育,公共サービスへの展開
文献
人名索引
事項索引
監訳者あとがき