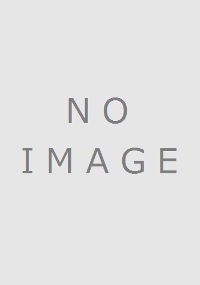プラムディヤ・アナンタ・トゥールとその時代(上)
出版社: めこん
- 二〇世紀アジアを代表する作家プラムディヤ・アナンタ・トゥールの世界初の評伝。作家は、いかに生き、いかに闘ったのか。
- 二〇世紀アジアを代表する作家プラムディヤ・アナンタ・トゥールの世界初の評伝。作家は、いかに生き、いかに闘ったのか。
- 二〇世紀アジアを代表する作家プラムディヤ・アナンタ・トゥール。その八一年の生涯はオランダの植民地支配、独立後の新国家建設、スハルトによる独裁的支配まで、インドネシアが歩んできた歴史と重なる。その間、彼は三度におよぶ牢獄と流刑生活のなかで、さまざまな物語を紡ぎだし、作品は四〇を超える言語に翻訳され世界的な名声を獲得した。作家はいかに誕生し、いかに生き、いかに闘ったのか。豊富な資料をもとに、彼の生涯と時代との格闘をいきいきと描きだす世界初の本格評伝。
一人の作家の伝記がそのまま一国の歴史に重なる。
反体制派であった作家の視点と権力者のふるまいは対立するから、この本には弁証法的な奥行きが生じて真の歴史となった。
投獄に耐えて書き継がれた彼の作品群は国の歩みの証言でもある。池澤夏樹 - 第一章 故郷ブロラ 一九二五年ー一九四二年
故郷の風景
父と母の肖像
ブディ・ウトモ学校
絶対的家長、あるいは左派ナショナリスト
《インドネシア》の発見
最初に戦場に立つ者
ブディ・ウトモ学校で学ぶ
割礼とムスリムの夢
私学校条例反対闘争
「それから彼が生まれた」
読書
父と母の亀裂
闘う父、変節する父
進学の夢
スラバヤのラジオ専門学校で学ぶ
『ブロラからの物語』
第二章 日本軍占領下で 一九四二年ー一九四五年
ジャワ島攻略戦
「あきらめた彼女」
「解放者」ニッポン
占領下の父トゥール
母の死と旅立ち
ジャカルタに出る
タマン・デワサで学ぶ
同盟通信社で働く
上司・俣野博夫
「私の大学」
日本軍占領下で
インドネシア語の整備と普及
タマン・デワサの閉校
ロームシャとヘイホ、ケンペイタイ
啓民文化指導所と武田麟太郎とハイリル・アンワル
文学と検閲
速記者になる
同盟通信社に復帰する
退職、放浪、そして終戦
第三章 独立革命期 一九四五年ー一九四九年
インドネシア独立宣言
革命の始まり
アナーキーな渦のなかで
アミル・ハムザの死
共和国軍に加わる
「スラバヤ」と「復讐」
『ブカシ川の岸辺で』
除隊をめぐって
『自由インドネシアの声』
リンガルジャティ協定
最初の投獄と「ガドガド」
ブキドゥリ刑務所と『無力な者たち』
釈放のとき
『無力な者たち』と『死の家の記録』
創作活動へ
「ブロラ」と「クランティル通り二十八番」
スタインベックとサロイヤン
『追跡』と『ゲリラの家族』
主権移譲までの軍事と外交をめぐる戦い
ふたたびブロラから
第四章 文学と政治の間で 一九五〇年代
未完の革命
ブキドゥリ刑務所を出る
結婚
父の死と『夜市ではなく』
新たな家長として
バライ・プスタカに勤める、あるいは四五年世代について
配信代行業ドゥタ
グランガン・グループとレクラ
「文学における美」「苦いリアリズム」「道具としての文学」
攻撃的論争家
オランダ行き
『汚職』と『金歯の恋人ミダ』
バンドゥン会議と文化自由会議
五五年総選挙で白票を投じる
離婚、そして再婚
『ジャカルタからの物語』
マクシム・ゴーリキー『母』 を訳す
中国訪問
「革命的文学をめざして」
文学から政治へ――吊り橋と大統領構想
『南バンテンでのある出来事』
第一回アジア・アフリカ作家会議に出席する
中国再訪
レクラに加入する
「ある農夫の死」