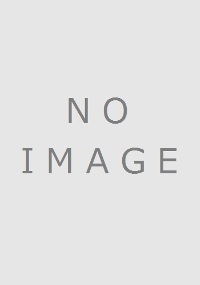境界線を曖昧にする ケアとコミュニティの関係を耕す
出版社: ブルーブラックカンパニー
- 一人ひとりが望む健康な暮らしを送るには、「医療・福祉」と「人」と「まち」のあいだにどんな「つながり」が必要なのだろうか――。訪問看護ステーションやコミュニティカフェを運営してきた理学療法士の実践と思考の記録。
- 《一人ひとりが望む健康な暮らしを実現するには、「医療・福祉」と「人」と「まち」のあいだにどんな「つながり」が必要なのだろうか――。「医療・福祉の専門職」と「まちの一住民」という二つの視点を往復し、人と人との「つながり」のかたちを模索しながら訪問看護ステーションやコミュニティカフェを運営してきた理学療法士の実践と思考の記録》
二つの総合病院と訪問看護ステーションに勤務した著者は、医療の閉鎖性やパターナリズム(父権主義)に違和感を抱き、32歳で起業。医療と患者、医療と地域のより良い関係を目指し、東京都府中市を拠点に、訪問看護ステーションとコミュニティカフェの運営に乗り出した。
〈医療者に対する患者の遠慮が医療の世界をより一層閉鎖的にしていることを考えれば、病院などの医療機関が中心となって取り組んでも大きな変化は起こらないのでは?〉
〈医療と患者、医療と地域のあいだにある壁や関係の偏りを解消するためには、医療や福祉の専門職がまず白衣等のユニフォームを脱ぎ、お互いがまちで暮らす一住民として出会うことからはじめる必要があるのでは?〉
〈医療や福祉の視点でまちを見ることと、まちからの視点で医療や福祉を見ることを日常的に行き来すれば、それぞれが抱える課題がもっとリアルに見えてくるのでは?〉
――そんな仮説に基づき、「医療」と「暮らし」という二つの軸による事業を展開して10年。医療・福祉領域では新たに居宅介護支援事業も手がけるようになり、コミュニティ事業は近隣の空きアパート2棟へと拠点を広げた。この一帯とそこでの活動は「たまれ」と呼ばれ、アート、食、教育、子育てなど、多様なテーマの仕事や活動が多世代によって営まれている。
著者初の著作となる本書では、起業当初に直面した資金繰りの悪化やマネジメントの混乱などを経て、地域の人たちとの関わりを深めながら「場」が自走していくプロセスや、医療・福祉と地域住民との「関わりしろ」をつくってきたことが力を発揮したコロナ禍での取り組みなど、著者と仲間たちが格闘してきた軌跡を振り返る。また、ALS(筋萎縮性側索硬化症)を患う母やアルコール依存症の父との関係についても率直に綴り、「医療・福祉」と「人」と「まち」の「つながり」のかたちを問い直している。
【本書より】
僕たち医療や福祉の専門職の多くは、「目の前に困ってる人がいるなら、すぐに解決してあげなきゃ」と思う癖がついてるし、たくさんの「科学的に正しい選択肢」を持っている。でも、それってあくまでも医療というフィールドでの正しさであって、その人の人生の中での正しさとは限らない。だからこそ、「ゆらぎ」の視点が大事になる。そして「ゆとり」を持って関われることが、相手にとっての、その瞬間における答えを一緒に見つけていく上で欠かせないんだと思う。(第5章「弱く、淡く、ゆるやかなつながりの確かさ」より) - まえがき
第1章 まちと溶け合う訪問看護ステーション、誕生
訪問看護ステーションとカフェで「地域の空気を変える」
医療の魔法が解けた瞬間
白衣を脱いで、まちへ出よう
理学療法士が起業するには
訪問看護とスペシャルティコーヒー
第2章 おだやかならざる日々
マネジメント迷走録
母に降りかかった「死の宣告」
夢見る力と命の選択
[コラム] 父とアルコール依存
第3章 医療とさりげなく隣り合うコミュニティ
まちのセカンドリビング「フラットスタンド」
2拠点でのコミュニティ運営――「たまれ」という名の村づくり
[コラム] 「たまれ万博」という風景
隣町でコーヒーを手渡す――旧国立駅舎プロジェクトという実験
駅ナカスペース「武蔵野台商店」のはじまりと終わり
第4章 暮らしと医療の境界線をめぐって
コロナと暮らしと在宅医療――あのとき僕らは
インタビュー
医療から暮らしへ、暮らしから医療へ――それぞれの関わり方
[コラム] 専門性と市民性――介護予防の現場から
第5章 弱く、淡く、ゆるやかなつながりの確かさ
「わかりあえない」からはじまるコミュニケーション
「つながり」への違和感
「つながり」を時間軸で考える
たゆたう「つながり」――ただ、共にある関係
引用・参考文献
あとがき