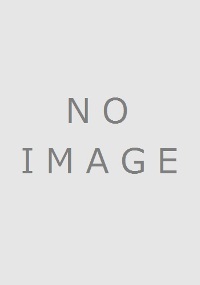“新聞のおばさん”と呼ばれた 高崎節子の闘い
出版社: 花乱社
- 「陽の当らぬ子供たち,小さな力のない者は
訴えることさえできない,その味方になるんだ」
高崎節子(1910-73)は,若き日々,植民地統治下の朝鮮や福岡で教鞭を執るかたわら小説「支那との境」,「山峡」を発表。戦後,労働省婦人少年局に勤め,新聞配達少年や働く女性たちに目を向け,労働環境の改善に奔走する。著書『混血児』,『人身売買』は社会を大きく揺るがし,それらの軌跡は男女雇用機会均等法・男女共同参画基本法へとつながった──。 - 序[日本近代文学研究者 尾形明子]
第一章 原点─植民地下朝鮮と文学との出合い
はじめに
一、生い立ち
二、福岡県女子専門学校から九州帝国大学聴講生へ
三、文芸雑誌『女人芸術』と「支那との境」
四、高崎印刷所と松本清張
五、結婚、そして小説「山峡」
第二章 福岡時代─教職から労働省婦人少年局へ
一、福岡女学校教職時代
二、福岡時代の活動
三、労働省婦人少年局福岡職員室主任へ
第三章 「混血児」「人身売買」問題を告発
一、労働省神奈川婦人少年室と「混血児」問題
二、労働省東京婦人少年室と「人身売買」問題
第四章 新聞配達少年、女性の労働環境の改善を啓蒙
一、新聞配達少年像の建立
二、ブラジル現地報告
三、「働く年少者の保護運動中央大会」とヘップサンダル事件
四、女性労働問題の啓蒙活動
五、東京婦人補導院へ
六、辞世の詩「さびたの道」
附録 素顔の高崎節子 『追悼集』より
高崎節子略年譜
あとがき