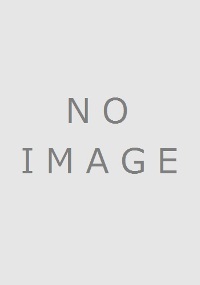民事訴訟目的論
出版社: 信山社出版
- 民事訴訟制度の目的=紛争解決に対し、紛争解決説の主唱者である兼子一の歴史認識や法認識、論理的構造にまで立ち入って批判的に検討
- 民事訴訟制度の目的=紛争解決に対し、紛争解決説の主唱者である兼子一の歴史認識や法認識、論理的構造にまで立ち入って批判的に検討する。
- ◆民事訴訟の目的とは何か ― 権利保護説からする紛争解決説の批判◆
民事訴訟制度の目的=紛争解決の捉え方に対し、紛争解決説の主唱者である兼子一の歴史認識や法認識、論理的構造にまで立ち入って検討。
◆本書より…「民事訴訟制度の目的=紛争解決の捉え方に対しては、これまで問題視されてきたが、全体としては、依然として紛争解決説が支持されている。その原因は、紛争解決説批判に不十分な点があったことも与かっているように思われる。」すなわち「この説の主唱者である兼子一の歴史認識や法認識、論理的構造にまで立ち入った検討が遺憾ながら充分に行われなかったのが原因であった。」 - 『民事訴訟目的論 ― 紛争解決説批判と憲法上の権利保護保障』(法律学の森シリーズ)
松本博之(大阪市立大学名誉教授) 著
【目 次】
◆序 本書の課題
1 民事訴訟の目的=紛争解決か
2 民事訴訟は市民の権利を保護しているか
3 本書の課題と考察の順序
(1) 本書の課題/(2) 考察の順序
◇◆第Ⅰ編◆◇ 民事訴訟制度の目的―紛争解決説の成立,その論理構造および種々の問題
◆第Ⅰ章 紛争解決説の登場
1 紛争解決説
2 日本国憲法下での紛争解決説=兼子・訴訟理論
3 兼子・訴訟理論は民事訴訟法学の金字塔か
◆第Ⅱ章 兼子・訴訟理論における法史的観点
1 兼子・訴訟理論の法史的理解による民事裁判
2 Ehrlichの見解
3 訴訟を通じての実体法の生成,ローマ法理解
(1) ローマ法のアクチオ理解/(2) litis contestatio
◆第Ⅲ章 紛争解決説に対する批判的見解
1 小室直人の批判
2 Max Weber, Hermann Jsay, Maine の見解
(1) M. Weberの見解/(2) Jsayの見解/(3) Maineの見解
3 伊東乾の批判
4 三ケ月章の紛争解決説と藤田宙靖の批判
(1) 藤田・三ケ月論争/(2) 三ケ月・紛争解決説に対する疑問/(3) 新堂幸司の反応
5 竹下守夫の見解
(1) 憲法との関連/(2) 竹下提案の評価
◆第Ⅳ章 自力救済から公的権利保護への過程
1 はじめに
2 復 讐
3 ローマ法と自力救済
(1) 種々の自力救済/(2) 正統な自力救済(legitime Selbsthilfe)/(3) 法律上の自力救済
4 中世ドイツにおけるフェーデ
(1) 復讐とフェーデ/(2) 騎士フェーデと神の平和運動,ラント平和令/(3) 非騎士フェーデ//(4) 贖罪金
5 ドイツ普通法時代の多数説とPuchta, Windscheidの見解
(1) ドイツ普通法/(2) 地方特別法/(3) プフタの見解/(4) 現行ドイツ法/(5) 国家の司法独占と権利保護
◆第Ⅴ章 兼子・訴訟理論の法論理的構造
1 裁判規準としての実体法
(1) 兼子・訴訟理論による私法の行為規範性の否定/(2) 裁判規範としての私法規範の反射的作用/(3) 兼子自身による行為規範性の承認/(4) 裁判による紛争解決
2 私法法規=裁判規範説の理由づけと問題点
(1) 法哲学の観点/(2) M. E. Mayerの見解/(3) Binderの見解/(4) Pferscheの見解/(5) 兼子・訴訟理論による裁判規範説の受容
3 訴訟的法考察方法
(1) 訴訟法律状態説/(2) 兼子・訴訟理論による訴訟法律状態説の受入れと訴訟法律状態説の発展
4 裁判所による権利の「実在化」
(1) 確定判決による権利の実在化/(2) 兼子・訴訟理論の基礎となったドイツ法文献/(3) 権利実在化の内容とその批判
5 第Ⅴ章のまとめ
◆第Ⅵ章 兼子・訴訟理論とJ. Goldschmidtの訴訟法律状態説
1 「訴訟法律状態説」
(1) Goldschmidtのローマ法の観念/(2) 訴訟法律関係説の否定と法状態による訴訟把握/(3) 訴訟的法考察方法/(4) 法的状態としての訴訟/(5) 取効的訴訟行為と与効的訴訟の行為の分類/(6) 既判力
2 訴訟法律状態説の批判
(1) 訴訟法律関係説からの批判/(2) 訴訟的法考察方法に対する批判/(3) 民事訴訟の目的との関係
3 日本における賛否
(1) 中野貞一郎による批判/(2) 三ケ月章による批判/(3) 訴訟法律状態説に積極的意味を認める見解
4 兼子・訴訟理論との比較
(1) 基本的差異/(2) 既判力論
◆第Ⅶ章 兼子・訴訟理論とSauerの法創造説
1 Wilhelm Sauerの一般訴訟法理論
(1) 裁判官による法の形成,法のイデーの形成/(2) Sauerの考察方法
2 Sauerによる不当判決(誤判)の否定
3 兼子・訴訟理論とSauer
◆第Ⅷ章 兼子・訴訟理論の評価と紛争解決説の諸問題
1 新堂・訴訟理論による高い評価
(1) 経験主義・実証主義的考察か/(2) Bulowは経験主義的,実証主義的考察を行ったか
2 藤田宙靖による批判
(1) 紛争解決説=法創造説/(2) 問題点/(3) 法治国家による権利保護の要請
3 訴訟法と実体法の関係をめぐって
(1) 訴訟法律関係説について/(2) 権利保護請求権説による私法の従属化か/(3) 訴訟法律関係説否定の意味するもの
4 主観的権利の否定
(1) 主観的権利とその体系としての私法の否定/(2) 私法の構成要素としての主観的権利/(3) 主観的権利の重要性
5 紛争解決説と訴訟要件としての法的利益
(1) 紛争解決請求権と本案判決請求権の等値/(2) 本案判決を求める法的利益
6 「確認訴訟原型観」をめぐって
(1) 問題の所在/(2) 確認訴訟原型観/(3) 確認訴訟原型観に対する批判的見解/(4) 私 見
7 兼子・訴訟理論における訴訟物
(1) 旧実体法説/(2) 原告の主張する請求原因からの裁判所による具体的権利の演繹
8 「相手方の援用しない当事者の自己に不利な事実の陳述」
(1) 兼子・訴訟理論と判例/(2) 兼子・訴訟理論の理由づけ
9 兼子・訴訟理論と証明責任
(1) 法規不適用説と証明責任規範説/(2) 私 見
10 兼子・訴訟理論と上訴制度の目的
(1) 控訴審の目的/(2) 控訴審の事後審的運営/(3) 控訴審の事後審的運営と最高裁
◆第Ⅸ章 民事訴訟の目的と憲法上の権利保護保障
1 訴訟目的を論じる意味
2 民訴法学の体系構築
(1) 小山昇による訴訟目的と訴訟法の体系構成との関連の指摘/(2) 紛争解決説と体系的観点/(3) 民事訴訟法の体系と訴訟目的論/(4) 私 見
3 民事訴訟制度の目的と民事訴訟法の解釈指針
(1) 出発点としての憲法/(2) 法的審問請求権の憲法上の保障/(3) 司法付与請求権,実効的権利保護請求権/(4) 憲法上の権利保護保障と私法秩序維持説/(5) 憲法上の権利保護保障と紛争解決説/(6) レヒト(Recht)の保護・実現
4 「あるべき姿の民事訴訟の目的」――新堂・訴訟理論
(1) 新堂・訴訟理論による新たな観点からの訴訟目的/(2) 民訴法の解釈指標としての訴訟目的
5 社会的関心の高い事件と民事訴訟のかかわり方,裁判による法形成問題
(1) 新堂・訴訟理論の問題提起/(2) 私法秩序維持説と手続保障/(3) 紛争解決説と法形成
6 多様な訴訟目的説の登場と紛争解決説内部の一定の変化
(1) 多元説/(2) 手続保障目的説/(3) 紛争の法的解決説/(4) 適正,迅速かつ経済的な手続による紛争解決説/(5) 目的論棚上げを主張する見解または訴訟目的論を不要とする見解/(6) 公共サービス説
◇◆第Ⅱ編◆◇ 民事訴訟における権利保護の必要と利益 ― 紛争解決説による国家的利益からの解釈とその批判的考察―
◆第Ⅰ章 訴えの利益または権利保護の必要
1 法律状態
2 通 説
3 本編の課題
◆第Ⅱ章 ドイツ民事訴訟における「権利保護の必要」論の展開と問題点
1 権利保護請求権説
2 Erich Bleyによる訴訟要件としての法的利益
3 第三帝国期(ナチス政権下)における権利保護の必要の意味転換
4 第二次世界大戦終結後の学説状況
(1) Schonkeの権利保護の必要論/(2) 判決手続/(3) Schonkeにおける公益の重視
5 通説・判例に対する批判,反対説
(1) 批 判/(2) Schumannのテーゼ/(3) 実体法と訴訟法との混交,他の訴訟要件に代わる権利保護の必要の否定/(4) 法的救済方法の競合/(5) その他の権利保護の必要の機能
6 ドイツ法についてのまとめ
◆第Ⅲ章 日本における訴えの利益または権利保護の必要の捉え方
1 兼子・訴訟理論
2 三ケ月・訴訟理論
(1) 司法制度運用における国家的利益としての権利保護の利益/(2) Schönkeの見解との類似性
3 その他の代表的学説
(1) はじめに/(2) 小山昇と新堂幸司の見解/(3) 山木戸克己の見解/(4) 山本弘の見解
4 一般的訴訟要件としての訴えの利益または権利保護の必要・利益
(1) 日本の権利保護の必要・利益論の系譜/(2) 個別訴訟への国家の利益,社会の利益の顧慮の問題性
5 将来の給付の訴えにおける権利保護の必要
◆第Ⅳ章 裁判実務の動向
1 継続的不法行為における将来請求
(1) 名古屋新幹線訴訟/(2) 名古屋地裁の判決/(3) 控訴審判決/(4) 将来の給付の訴えの必要性と請求の理由具備性
2 大阪国際空港騒音訴訟の最高裁大法廷判決
(1) 差止請求訴訟の却下/(2) 将来の損害賠償請求の訴えの却下
3 確認の利益
(1) 判例および通説による原則/(2) 遺産確認の訴え/(3) 具体的相続分の確認を求める訴えの適法性/(4) 過去の権利または法律関係の存否の確認の適否/(5) 過去の法律行為の無効確認の適否/(6) 確認の訴えの補充性/(7) 判例の評価
4 形成の利益
(1) 原則と例外/(2) 形成の効果の遡及
5 第Ⅳ章のまとめ
◆第Ⅴ章 原告の利益への回帰の必要性
1 明文規定なく権利保護の必要を訴訟要件として原則化することの問題性
(1) 統一的な明文規定の不存在/(2) 不特定,不正確さ/(3) 本案判決回避の可能性の排除
2 紛争解決説の問題性
3 訴訟経済の原則との関係
(1) 訴訟経済の原則/(2) 条件つき本案判決要件としての権利保護の必要
・おわりに
◇◆第Ⅲ編◆◇ 雉本朗造と民事訴訟法理論 ―「当事者適格」概念の形成とその問題性―
・はじめに
◆第Ⅰ章 雉本朗造
1 経 歴
2 ドイツでの足跡
3 帰国後の研究
◆第Ⅱ章 雉本朗造の民訴法理論
1 はじめに
2 民事訴訟における実体適格と訴訟追行権
(1) 実体適格/(2) 訴訟追行権
3 雉本朗造による「当事者適格」概念の提唱と兼子一による受容
(1) 雉本朗造による「当事者適格」概念の提唱/(2) 兼子一による当事者適格概念の受容
◆第Ⅲ章 当事者適格概念の一般化と問題の発生
1 当事者適格概念の一般化
(1) 特許侵害訴訟/(2) 執行関係訴訟/(3) 口頭弁論終結後の承継人への既判力の拡張
2 種々の問題
(1) 実体権の帰属の主張による訴訟追行権/(2) 国際民事訴訟における訴訟追行権
◆第Ⅳ章 分 析
1 実体適格概念の必要性
2 憲法上の権利保護請求権
3 「当事者適格」についての新たな見解とその批判
(1) 日本固有の「当事者適格」概念を主張する見解の登場/(2) 新たな見解に対する批判/(3) 訴訟追行権と判決効
・おわりに
◇要約と展望
・あとがき
◆索 引
事項索引/人名索引/判例索引