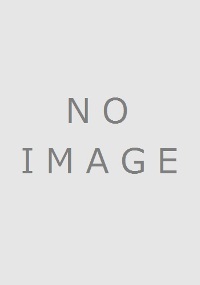問いの技法
出版社: 青弓社
- 教育での「問う力」、ビジネスでの「質問力」や「聞き方」など、問いは様々なシーンで重要視されています。私たちは会話や文章、プレゼンなどで日常的に多くの問いを立てて質問し、問いにうまく答えようとすることでコミュニケーションを成り立たせています。
「いつ東京に来たの?」「食後にコーヒーを飲むのはなぜ?」という日常会話、「あのプロジェクトはうまくいったの?」「売り上げが落ちたのはなぜ?」という仕事のやりとり、「国会はこの法律を成立させるか否か」という社会的な問い――。
本書では、実体験から問いの立て方を紹介するのではなく、「問いの理論」に基づいて「そもそも問いとは何か」をひもとき、多様な問いの分類整理からそれぞれの技術の説明、そして人工知能と問いというアクチュアルな問題までを射程に収めて解説します。
高校生や大学生が「いい問い」を立てるヒントが詰まっているのはもちろん、社会人のリスキリング(学び直し)としても役立つユニークな問いの教科書です。 - はじめに
第1部 問いを理解する
第1章 問いは答えの選択である
1 問いとは何か
2 答えを選択するということの意味
第2章 暗黙の問いを見つけ出す
1 問いの先取り
2 高度な問いの先取り
3 文章やプレゼンなどでの問いの先取り
4 暗黙の問いの重要性
第3章 問いの焦点をはっきりさせる
1 平叙文の焦点
2 問いの焦点
3 焦点を意識することの重要性
第4章 事実と評価を区別する
1 社会的な問い
2 事実と評価
3 社会的評価
4 社会的事実
第5章 事実と意見・主張を区別する
1 事実と主張の違い
2 意見と主張の違い
第6章 根拠と理由を区別する
1 二種類の「なぜ」
2 推論の問い
3 根拠と理由の区別
第7章 原因と理由を区別する
1 説明の問い
2 原因と理由の区別
3 原因を問う目的、理由を問う目的
4 二種類の理由?
第8章 「問いの世界」の全体像
1 記述の問い
2 社会的な問い
3 二次的な問い
4 心の問いと世界の問い
第2部 問いを立てる
第9章 問いを学ぶ
1 自分自身の問いをもつということ
2 問いを学ぶということ
3 問いを自分のものにする
第10章 問いに気づく
1 言葉に注意を払う
2 選択と否定を意識する
3 先取りされている問いを見つける
第11章 二次的な問いを立てる
1 まず意味がある答えを見つける
2 比較による「別の答え」の発見
3 「なぜ」の問いを仕分けるための確認の問い
4 焦点を明確にする
第12章 漠然とした問いを明晰化する
1 問いの語彙の使用
2 違いを問う
3 関係を問う
第3部 質問をする
第13章 質問について考えるための準備
1 問いとしての質問
2 質問の分類
第14章 正解がある質問――社会的な答えについての質問
1 事実を知る者と知識をもつ者
2 マスメディアによる質問
3 専門家への質問
第15章 正解を作るための質問――主張や意見についての質問
1 主張・意見を問うという考え方
2 多様性の期待と統一への志向
3 代議員は何を問うか
4 「陰謀論」にどう接するか
第16章 心を問う質問――理由についての質問
1 心を問う質問の難しさ
2 理由を問う質問の重層性
3 理由の多様性
4 質問する側の記述と質問される側の選択
補 章 人工知能と問い――生成AIとは何か
1 人工知能は本当に問いに答えているのか
2 人工知能は正解を見つけ出すことができるのか
おわりに