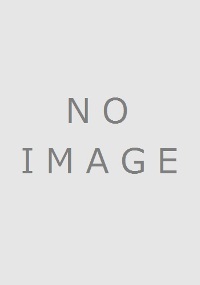授業と学級社会づくり 人権を基調に
出版社: 解放出版社
- 「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業、子どもが自立しつつ豊かにつながる学級。それをつくる考え方と実践的アイデアを提案。
- 子どもたちの「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業。一人ひとりが自立しながら豊かなつながりをもつ学級社会。これらをどうつくるのか。そのための考え方とさまざまな実践的アイデアを楽しく明快に提案するエッセイ集。
- 子どもたちの「主体的・対話的で深い学び」を実現する授業。一人ひとりが自立しながら豊かなつながりをもつ学級社会。これらをどうつくるのか。そのための考え方とさまざまな実践的アイデアを楽しく明快に提案するエッセイ集。
互いに学び合おうとする空気感が教室に漂い、子どもと教師が右往左往しながらも一コマの授業を共創する。少数の異質な意見も全体にシェアされる。そして、集団の中核に据えている子どもAが身を乗り出すようにして意見を述べる。このような姿の授業をめざしたい。
問題のない学級が健全な学級ではない。起こる問題を自分たちで納得がいく解決のできる学級が健全な学級である。
学級・学校社会とその文化は教師の占有物ではなく、子どもと共創し続ける「コモン(共有財)」ととらえたい。それには授業者と学習者の役割分担の固定化という伝統的なスタイルを超えた新たな教育的役割分担が追求されるべき。 - はじめに
○第一章 こんな授業に圧倒されたい
こんな授業に圧倒されたい
「学級社会」をふり返り高める授業
追求したい「授業のかたち」
子どもの見事なつぶやき
「子どもの立場」を尊重する授業づくり
授業中の「禁句」
ウェルビーイングについて考える授業
全校生に人権学習
天災は忘れないうちにやってくる
○第二章 納得できる学級づくりの方法
「学級開き」は二度ある
子どもが「豊かにつながる」ために
「学級通信」は学級社会の“有形文化財”
子どもの実像が鮮やかに見えてくる
二学期 めざしたい学級社会の姿
その「自己肯定感」は大丈夫か
「最近の学校はほめることばかり」
「自己有用感」という栄養素
実り豊かな最終章のために
○第三章 こうありたい!「教師のスタンス」
子どもが「主体的・対話的に学ぶ」条件
「納得のいく授業」のレベル
生身の「子ども研究」
「常識」を少し問うことから
二学期の授業は「五割削減」で
自分自身の「人権課題」
「先生なんかいらん」の本当の意味
○第四章 こんな「実践」をやってみたい
こんな「実践」をやってみたい
「生活知」と「学校知」の接続
「持ち味」と「持ち場」のマッチング
ある「イラスト画像」の深い意味
「アクション体験」の欠落
授業後の「延長戦」
「特別な体験」をした子どもたち
○第五章 忘れない! コロナ禍の「教訓」
子どもの琴線に触れる授業
探究学習の「リアルな素材」
弁当と給食と「学習ロス」と
新型「善玉おせっかい文化」のすすめ
全身が躍動する「学級文化活動」
五枚の「学級通信」
「教師冥利」は死語なのか
夏休みに孤立するヤング
○第六章 「きょう一日どんな良いこと起こるかな」
言い得て妙な「名文句」
受話器の向こうの一言
スーパーでの出来事から
「きょう一日どんな良いこと起こるかな」
「被尊の舞台」に立つ
奇跡の一年生物語
○第七章 人権を基調とした「学級社会づくりと授業」
人権を基調とした「学級社会づくりと授業」