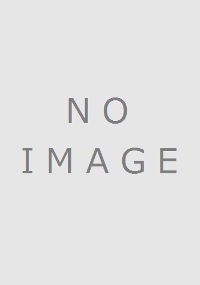定番漢詩教材考
出版社: 文学通信
- 漢詩は必ずしも中国由来のものばかりではなく、わが国の文学作品にも強く結びついている。では漢詩はどう日本で読まれてきたのか。そんな漢詩はどう教育のなかで教えられてきたのか。漢文教育の必要性をより客観的な観点から論じるための、読み歴史と教育の歴史がわかる。
定番化した「漢詩」教材を取りあげ、その受容状況と教材的な観点を柱として論じる。
日本における唐詩受容の変遷を、平安時代・五山時代・江戸時代・明治時代以降の諸書を通して詳細に俯瞰し、唐詩作品を教材的な観点から分析する。受容変遷については、精緻を極め、ときに戦争漢詩教材まで言及される。明治時代以降は平成、令和とつい最近のものまで視野に入る。
国語教育としては、近代教育における漢詩教材の取り扱いについて述べた「第一章 漢詩教育史―近代教育から漢詩創作指導までの道程―」は必読。国語教育としての漢文教材の位置づけに関して、考えるヒントを示す。漢詩鑑賞指導についてのコラムも多数掲載。
王翰「涼州詞」、孟浩然「春暁」、王維「陽関三畳」、李白「白帝城」、崔顥「黄鶴楼」、杜甫「春望」、張継「楓橋夜泊」、白居易「香炉峰下」などの唐代名詩の受容状況と、教育の歴史がわかる本です。
【本書は国語教科書においてもなじみのある唐代の定番漢詩教材を取りあげて考察したものである。中国においてはそれぞれの詩語をもとに後世の漢詩作品が生み出されたことは論を俟たない。ただし、わが国では各漢詩人に立脚した作品論が多く報告されているものの、各詩語からの考察がなされることはほとんどなかった。これが本書の他書とは異なる画期的な点であろう。本書を一読していただければ、わが国で唐詩をどのように受容して日本漢詩を生み出してきたのか体感していただくことができるものと思われる。】……「序章 日本人と漢詩」より - 序 章 日本人と漢詩
一 はじめに
二 漢詩の歴史
三 わが国における漢詩文化
四 近代以降の漢詩研究─唐詩と江戸漢詩を中心に─
五 本書の構成と特徴
第一章 漢詩教育史─近代教育から漢詩創作指導までの道程─
一 はじめに
二 近代教育における漢詩文の取り扱い
三 諸家における漢詩教育観
四 筆者の考える漢詩教材の意義
五 まとめとして
コラム 日本漢詩の伝統と拙詩
第二章 平仄記号─韻書と詩法書の変遷─
一 はじめに
二 漢詩の規則と教育的意義
三 中古・中世期の漢詩創作教材
四 近世期の漢詩創作教材
五 まとめとして
第三章 王翰「涼州詞」─辺塞詩における江戸人の受容─
一 はじめに
二 王翰「涼州詞」と西域文物
三 唐詩注釈書における「涼州詞」解釈
四 文学作品における「涼州詞」受容─近世から近代まで─
五 まとめとして
コラム 漢詩「勧酒」教材考─平仄・韻目に着目した部分的漢詩創作の取り組み─
第四章 孟浩然「春暁」─結句「花落知多少」の定訓─
一 はじめに
二 孟浩然「春暁」について
三 結句「花落知多少」和書用例─中世から現代まで─
四 結句「花落知多少」をめぐって─雑誌『解釈』を中心に─
五 まとめとして
第五章 王維「陽関三畳」─送別詩における歌唱法の受容─
一 はじめに
二 王維「送元二使安西」と《陽関詩》漢籍用例
三 《陽関詩》和書用例─中世から近代まで─
四 歌い継がれる《陽関曲》─歌唱法と明清楽をめぐって─
五 まとめとして
コラム 楽漢的指導案─親しむための漢語指導─
第六章 李白「白帝城」─郷土漢詩教材としての視点─
一 はじめに
二 李白「早発白帝城」と杜甫「白帝城」二詩
三 「白帝城」和書用例─近世から近代まで─
四 郷土漢詩教材としての「白帝城」
五 まとめとして
第七章 崔顥「黄鶴楼」─仙人譚の詩における受容─
一 はじめに
二 「黄鶴楼」三詩と漢籍用例
三 詩偈としての「黄鶴楼」─宋代から中世五山まで─
四 「黄鶴楼」和書用例─中世から近代まで─
五 まとめとして
コラム 韻文指導ともじり
第八章 杜甫「春望」─『おくのほそ道』における松尾芭蕉の視点─
一 はじめに
二 『おくのほそ道』における「春望」受容
三 「春望」和書用例─中世から近世まで─
四 芭蕉の古典受容における国語教育的視点
第九章 張継「楓橋夜泊」─旅愁の詩における通史的な受容─
一 はじめに
二 張継「楓橋夜泊」漢籍用例
三 中世における「楓橋夜泊」─五山文学としての受容─
四 近世における「楓橋夜泊」─勝景詩としての心象風景─
五 近代における「楓橋夜泊」─実景としての寒山寺─
六 まとめとして
コラム 唐詩「芙蓉楼送辛漸」を用いた実践授業─「平仄」・「詩眼」に着目して─
第十章 白居易「香炉峰下」─清少納言《対雪捲簾》故事─
一 はじめに
二 中古・中世期の白居易《対雪捲簾》故事受容
三 近世期の清少納言《対雪捲簾》故事受容
四 近世・近代教育における《対雪捲簾》故事─「清少納言」賢女像の確立─
五 まとめとして
あとがき
参考文献
初出一覧