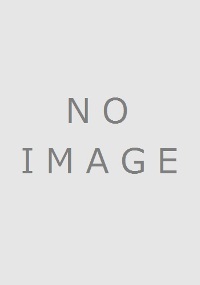学問から「いま」を見通す
出版社: 春風社
- 先の見通しが容易に立たない「いま」という困難な時代において、世界をどのように捉え、向き合えばよいのか。人文科学・社会科学・自然科学にまたがる多彩な学問分野の気鋭の研究者が、それぞれの分野における「いま」を掴み取ろうとした記録。
- はじめに 激動の世界と対峙する「見取り図」のために〔山﨑真之〕
第1部 健康・生活
第1章 コロナ禍、ヴィーガニズム、異星人―マーガレット・アトウッド「わんぱくグリゼルダ」における食の問題〔坪野圭介・今井祥子〕
第2章 ハイブリッド・ジャパニーズ―ノブレストランの料理とデザイン〔今井祥子〕
第3章 生活に根ざした健康情報を共に作る―災害公衆衛生と認知症の事例から〔黒田佑次郎〕
第4章 ギャンブル行動症に対する心理学的支援の現状と今後の課題―エビデンス・ベイスト・プラクティスの展開のために〔田中佑樹〕
第5章 子どもの集団適応の向上を目的とした、子どもと支援者および養育者との良循環の形成―行動論的アプローチに基づく相互作用の検討〔堀川柚〕
第6章 社会人生活の適応を促進する大学生の職業選択行動とは―支援のあり方の一考〔輕部雄輝〕
第2部 情報・言語
第7章 スマートツーリズムでの偶然の出会い―ICTによる観光者の自由の制限と創出からの考察〔澁谷和樹〕
第8章 「推し活」の光と闇―「推し活」に関する記事の内容分析〔市村美帆〕
第9章 生成AIや機械学習の発展は外国語学習を不要なものにするのか―機械翻訳の歴史的発展と外国語学習への応用に向けた検討〔内田翔大〕
第10章 ウェルビーイングに根差した大学英語教育―学生の積極的な学びを促すヒント〔山本貴恵〕
第11章 自律した英語学習者の育成を目指して―英語教育における内省活動とは〔辻るりこ〕
第12章 一人称複数we―複数のIを意味することはあるのか?〔松田麻子〕
第3部 地域・交流
第13章 観光は地域をいかに変えるか―カンボジア・シアヌークビルにおける観光空間の素描〔板垣武尊〕
第14章 無形文化遺産登録がもたらしたもの―中国・安徽省黄山市の「徽州祠祭」を事例に〔李崗〕
第15章 あらゆるものとは「調和」できない―アメリカ先住民ナヴァホ保留地におけるもめごとの対処と風通しのいい他者〔渡辺浩平〕
第16章 経済人類学を通じた人間性の探求―ミクロネシアのランク社会における存在承認の事例から〔河野正治〕
第17章 生物多様性の損失に立ち向かう―研究および地域住民それぞれの目線からの検討〔竹下和貴・石垣裕貴〕
第18章 Uターン者が紡ぐネットワーク―奄美大島瀬戸内町古仁屋における化粧まわし職人のライフストーリーを事例に〔山崎真之〕
おわりに 学問の歩き方 知的関心をひろげる読書のために〔坪野圭介〕