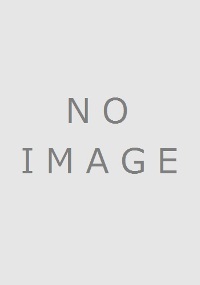国家と海洋の国際法 下巻
出版社: 信山社出版
- 国際法・海洋法等、69名の研究者が集い、激動の国際社会を多角的視点から考究。【下巻】第2部 海洋法(国家管轄権/安全保障等)
- 国際法・海洋法等、69名の研究者が集い、激動の国際社会を多角的視点から考究。【下巻】第2部 海洋法(国家管轄権/安全保障等)
- ◆上巻・下巻にわたる圧巻の柳井先生米寿記念◆
国際法・海洋法等、69名の研究者が集い、激動の国際社会を多角的視点から考究。上巻・下巻にわたる圧巻の米寿記念。
【下巻】武力紛争[第1部 国際法]■第2部 海洋法■海域と海洋地形/海洋と国家管轄権/海洋と人権/海洋と環境/海洋と紛争解決/海洋と安全保障/日本と海洋法/地球規模課題と環境 - 『国家と海洋の国際法 ― 柳井俊二先生米寿記念(下巻)』
浅田正彦・植木俊哉・尾﨑久仁子 編
【目 次】
・はしがき
◆第1部◆ 国際法(上巻から続く)
◆Ⅷ◆ 武力紛争
◆36 武力紛争とテロリズム犯罪の訴追・処罰について―2023年のガザ紛争を例として〔尾﨑久仁子〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 国際犯罪としてのテロ犯罪
Ⅲ テロ犯罪の訴追・処罰に関する国際法
Ⅳ 国内裁判所におけるテロ犯罪の処罰と国際法
Ⅴ おわりに
◆37 国際法上の武力紛争の「終わり」再考―ロシア・ウクライナ戦争収束への取り組みを軸として〔坂本まゆみ〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 国際法上の武力紛争の「終わり」の現状
Ⅲ ロシア・ウクライナ戦争の経緯と法的位置づけ
Ⅳ ロシア・ウクライナ戦争収束への道程
Ⅴ おわりに
◆38 「トルーマン・ショウ」の終焉―イスラエル=パレスチナ紛争における当事者の等価値の決定主体性(agency)の回復と国際法解釈コミュニティーの職業的誠実さ(integrity)の模索を通じて〔高柴優貴子〕
Ⅰ 問題意識
Ⅱ 従前の支配的議論に見るパレスチナの決定主体性の軽視
Ⅲ 勧告的意見(2024 年)と残された課題
Ⅳ ジェノサイド条約に基づく係争事件の制約
Ⅴ 「恒久的安全保障(permanent security)」問題
Ⅵ むすびにかえて
◆39 武力紛争被害者に対する非国家武装集団の賠償責任―新たな責任法の枠組と意義〔古谷修一〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 非国家武装集団の賠償責任に関する理論状況
Ⅲ 非国家武装集団の賠償に関する実行
Ⅳ 非国家武装集団の国際責任論
Ⅴ 結 び
◆40 1924年ジュネーヴ議定書の賠償条項〔大森正仁〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ ジュネーヴ議定書採択までの経緯
Ⅲ ジュネーヴ議定書の採択及び条文の構成
Ⅳ 意義及び評価
Ⅴ 結びにかえて
◆第2部◆ 海洋法
◆Ⅰ◆ 海域と海洋地形
◆41 排他的経済水域・大陸棚に設置された海洋人工物に対する沿岸国管轄権〔西村 弓〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ EEZ・大陸棚における海洋人工物設置に関する国連海洋法条約の枠組み
Ⅲ 境界未画定海域における海洋人工物の設置
Ⅳ おわりに
◆42 「大陸棚単一論」の再検討〔西本健太郎〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 国際判例における大陸棚単一論の展開
Ⅲ 200海里以遠の大陸棚の独自性の再認識
Ⅳ おわりに
◆43 国際航行に使用される海峡に関する法的課題―通過通航権が適用されない海峡の認定を中心に〔下山憲二〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 海峡における通航制度の発展
Ⅲ 国連海洋法条約の関連規定
Ⅳ おわりに
◆44 境界未画定海域における海底資源の共同開発―半閉鎖海の事例の検討〔竹内明里〕
Ⅰ 序
Ⅱ 境界未画定海域の鉱物資源の共同開発
Ⅲ 境界未画定の半閉鎖海における大陸棚鉱物資源共同開発を巡る法的論点
Ⅳ 国家実行
Ⅴ おわりに
◆45 マーシャルズ201号事件―国連海洋法条約第121条3項の解釈と米国〔加々美康彦〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ マーシャルズ201号事件
Ⅲ 国連海洋法条約第121条3項の解釈と米国
Ⅳ おわりに
◆Ⅱ◆ 海洋と国家管轄権
◆46 船舶制度の国際法構造―社会通念の陥穽と海洋空間における組織的集合体の機能
〔黒﨑将広〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 特別制度上の「船舶」
Ⅲ 一般制度上の「船舶」
Ⅳ おわりに
◆47 自動運航船に対する旗国の義務〔竹内真理〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 国連海洋法条約上の「船舶」
Ⅲ 旗国の義務に対する自動運航船の影響
Ⅳ おわりに
◆48 水中文化遺産の法的保護―沈没軍艦を素材として〔小山佳枝〕
Ⅰ 序 文
Ⅱ 一般国際法における沈没軍艦の取り扱い
Ⅲ 水中文化遺産保護条約における沈没国家船舶の取り扱い
Ⅳ 結 論
◆Ⅲ◆ 海洋と人権
◆49 海洋における抗議活動と国際法―国連海洋法条約附属書Ⅶ仲裁裁判所アークティック・サンライズ号事件裁定と欧州人権裁判所Bryan対ロシア判決を手掛かりにして〔小島千枝〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 海洋における抗議活動とは
Ⅲ 海洋における抗議活動に関連する国際法
Ⅳ アークティック・サンライズ号事件における海洋法と人権法の適用
Ⅴ NORI-D Area事件
Ⅵ 結 論
◆50 国連海洋法条約第293条1項の「国際法の他の規則の適用」の限界と可能性―海洋法と人権法の交錯・相互作用の視点からの一考察〔田中清久〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 2つの仲裁判断に関する従来の評価
Ⅲ 3つの場合・類型
Ⅳ 限 界
Ⅴ 可能性
Ⅵ おわりに
◆Ⅳ◆ 海洋と環境
◆51 海域における環境犯罪の国際的規制―領海外におけるプラスチックごみ汚染についての旗国以外の国の刑事的規制を手がかりに〔石井由梨佳〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 国連海洋法条約とプラスチックごみによる海洋汚染の規制
Ⅲ 刑事的規制の意義と限界
Ⅳ おわりに
◆52 深海底鉱物開発の「モラトリアム」提案について―国連海洋法条約第145条と「2年ルール」に注目して〔佐俣紀仁〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ モラトリアム提案までの経緯と現状
Ⅲ モラトリアム提案の内容と法的根拠
Ⅳ 若干の検討
Ⅴ おわりに
◆53 国家管轄権外区域の海洋生物多様性に関する新たな国際ルールの成立―BBNJ協定の交渉経緯,国際法上の論点,今後の課題〔下飼手一郎〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ BBNJ協定の概要
Ⅲ 採択に至る経緯
Ⅳ 交渉過程での主な争点
Ⅴ BBNJ協定の国際法上の論点
Ⅵ BBNJ協定の今後の課題
Ⅶ おわりに
◆54 国家管轄権外の生物多様性の保存に関する協定(BBNJ 協定)の実相と今後の課題〔都留康子〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 国家管轄権外の生物多様性議論への前奏
Ⅲ 本会議の議論
Ⅳ BBNJ協定の内容と論点
Ⅴ 環境条約としてのBBNJ,そして,未決の問題
Ⅵ おわりに
◆Ⅴ◆ 海洋と紛争解決
◆55 国連海洋法条約第15部の運用〔青木 隆〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 海洋法条約第15部の概要とその背景
Ⅲ 第1節 他の平和的手段を利用する合意による第15部適用の停止または排除
Ⅳ 第2節 拘束力を有する決定を伴う義務的手続
Ⅴ 第3節 第2節の規定の適用に係る制限及び除外
Ⅵ むすびにかえて
◆56 国連海洋法条約第15部の義務的裁判制度における第3節の役割に関する一考察―第297条及び第298条に関する先例を手掛かりとして〔河野真理子〕
Ⅰ 序
Ⅱ 第15部の下での義務的裁判制度の要件と第298条の下での各国の宣言
Ⅲ 第297条と第298条の起草経緯
Ⅳ 第297条と第298条に関する先例
Ⅴ おわりに
◆57 国際海洋法裁判所の暫定措置要件〔玉田 大〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ ITLOS暫定措置の特徴
Ⅲ 管轄権要件
Ⅳ 権利要件
Ⅴ 緊急性要件
Ⅵ 海洋環境保全と「予防的アプローチ」
Ⅶ 客観訴訟型暫定措置
Ⅷ おわりに
◆58 COSIS勧告的意見が海洋法の漸進的発展に与える影響―国際海洋法裁判所大法廷の勧告的管轄権をめぐる一考察〔本田悠介〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ COSISによる勧告的意見の要請とその法的基盤
Ⅲ ITLOS大法廷の勧告的管轄権をめぐる学説の展開
Ⅳ おわりに
◆59 ICJの選択条項受諾宣言における「他の解決方法に合意した紛争」留保の意義―インド洋海洋境界画定事件を中心に〔石塚智佐〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ PCIJ及びICJの先例
Ⅲ インド洋海洋境界画定事件先決的抗弁判決
Ⅳ 「他の解決方法に合意した紛争」留保の実効性
Ⅴ おわりに
◆60 英仏大陸棚仲裁裁判再考〔三好正弘〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ ルネ=ジャン・デュピュイ教授に質した事項
Ⅲ 英仏大陸棚仲裁裁判の意義・問題点
Ⅳ 自然延長論の相対化
Ⅴ 北東アジア海域の境界画定への含意
Ⅵ おわりに
◆Ⅵ◆ 海洋と安全保障
◆61 Society 5.0と安全保障―「平時」における海底ケーブルの保護〔佐藤義明〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ Society 5.0の構築と強靱性
Ⅲ 海底ケーブルの敷設
Ⅳ 平時における海底ケーブルの保護
Ⅴ おわりに
◆62 海上阻止活動の根拠としての自衛権の「拡張的・修正主義的」解釈について〔新井 京〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 「拡張的・修正主義的」自衛権理論
Ⅲ 海洋における「拡張的・修正主義的」自衛権理論
Ⅳ 「昔ながらの曖昧さ」?
Ⅴ 2001年以降の「新たな」慣行?
Ⅵ むすびに
◆Ⅶ◆ 日本と海洋法
◆63 日本による直線基線制度の採用とその背景〔酒井啓亘〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 日韓漁業協定における直線基線問題
Ⅲ 直線基線採用をめぐる日本政府の方針
Ⅳ 日本による直線基線の採用
Ⅴ おわりに
◆64 海洋環境保護における国家の義務―福島第一原子力発電所からのALPS処理水の海洋放出を契機として〔岡松暁子〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 国家の海洋環境保護義務
Ⅲ 福島第一原子力発電所からのALPS処理水海洋放出を巡る法的見解
Ⅳ ALPS処理水の海洋放水にかかるUNCLOS上の国家の義務
Ⅴ 結 び
◆65 日韓大陸棚境界画定への調停の利用可能性〔瀬田 真〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 大陸棚境界画定における調停の実践
Ⅲ 調停による日韓の大陸棚境界画定
Ⅳ おわりに
◆Ⅷ◆ 地球規模課題と環境
◆66 国際環境法原則の存在証明―非後退Non-Regression原則を例として〔兼頭ゆみ子〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 非後退原則とは何か
Ⅲ 非後退原則の存在証明
Ⅳ おわりに
◆67 国際環境法における協力義務の意義〔佐古田彰〕
Ⅰ 問題の所在
Ⅱ 協力義務に言及する国際環境法分野に関する主な文書と裁判例
Ⅲ 国際環境法における協力義務の法的性格
Ⅳ 国際環境法における協力義務の意義
Ⅴ 結 論
◆68 気候変動訴訟―気候変動問題の人権概念への変遷と気候変動交渉における今後の課題〔山田和花奈〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 気候変動分野における先進国による義務の変遷
Ⅲ 国際裁判所における勧告的意見―気候変動に関する義務
Ⅳ 気候変動訴訟における気候変動問題の人権概念への変遷
Ⅴ おわりに―気候変動訴訟と気候変動交渉における今後の課題
◆69 気候変動についての覚書〔芹田健太郎〕
◇柳井俊二先生 略歴・業績
◇柳井俊二先生 主要著作