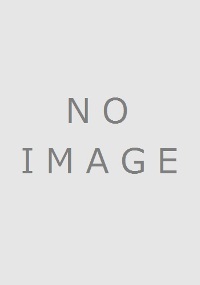国家と海洋の国際法 上巻
出版社: 信山社出版
- 国際法・海洋法等、69名の研究者が集い、激動の国際社会を多角的視点から考究。【上巻】第1部 国際法(総論と歴史/国家管轄等)
- 国際法・海洋法等、69名の研究者が集い、激動の国際社会を多角的視点から考究。【上巻】第1部 国際法(総論と歴史/国家管轄等)
- ◆上巻・下巻にわたる圧巻の柳井先生米寿記念◆
国際法・海洋法等、69名の研究者が集い、激動の国際社会を多角的視点から考究。上巻・下巻にわたる圧巻の米寿記念。
【上巻】■第1部 国際法■総論と歴史/国家管轄と承認/国際立法/ 国際組織と国際協力/人権/紛争解決/安全保障 - 『国家と海洋の国際法 ― 柳井俊二先生米寿記念(上巻)』
浅田正彦・植木俊哉・尾﨑久仁子 編
【目 次】
・はしがき
◆第1部◆ 国際法
◆Ⅰ◆ 総論と歴史
◆1 国際法の履行確保方法〔岩沢雄司〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 法の特徴としての強制
Ⅲ 国際法の履行を確保する様々な方法
Ⅳ おわりに
◆2 国際法における欠缺論の諸相―外交軸との接点と交錯〔吉田 脩〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 法の欠缺と国際法
Ⅲ 核兵器の威嚇又は使用の合法性事件
Ⅳ 結びに代えて
◆3 事務管理の国家間関係における適用可能性〔中谷和弘〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 比較法における事務管理:欧州参照枠草案(DCFR)における事務管理を中心に
Ⅲ 国際金融法分野における事務管理の適用可能性
Ⅳ 海事法・海洋法分野における事務管理の適用可能性
Ⅴ 宇宙法分野における事務管理の適用可能性
Ⅵ 国家責任法分野における事務管理の適用可能性
Ⅶ 外交・領事関係法分野における事務管理の適用可能性
Ⅷ 緊急時における他国民保護・救出に関する事務管理の適用可能性
Ⅸ 省 察
◆4 「チャゴス諸島海洋保護区事件」仲裁判決における禁反言の適用〔櫻井大三〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 事件の概要
Ⅲ ランカスター・ハウスの約束(LHU)の拘束力の問題に対する仲裁裁判所のアプローチ
Ⅳ 禁反言の適用をめぐる仲裁裁判所の判断
Ⅴ 仲裁裁判所の判断の特徴
Ⅵ おわりに
◆5 リヴァイアサンの意義と挫折―カール・シュミットのホッブズ論〔西 平等〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ ルネ・カピタンのホッブズ解釈
Ⅲ リヴァイアサンの意義と挫折
Ⅳ 結びにかえて
◆6 戦間期国際法学における連帯学派―レオン・ブルジョワとジョルジュ・セルの国際法思想〔西海真樹〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ レオン・ブルジョワの国際法思想
Ⅲ ジョルジュ・セルの国際法思想
Ⅳ おわりに
◆7 国際法における「文明の基準」の回帰〔松井芳郎〕
Ⅰ 問題提起
Ⅱ 近代世界システムにおける国際法
Ⅲ 伝統的国際社会における欧州国際法の形成と拡大
Ⅳ 外延の国の国際社会への受容:国家承認制度の役割
Ⅴ 現代国際法における「文明の基準」の衰退と「回帰」
Ⅵ 「文明の基準」の「回帰」?
Ⅶ グローバル化する世界における国際法の役割:結びに代えて
◆Ⅱ◆ 国家管轄権と承認
◆8 立法管轄権を規律する法規範―「自由(liberté)」に基底する「基本的立場」の対立に着目して〔森田章夫〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 立法管轄権をめぐる「基本的立場」の対立―「自由」とその基底状況
Ⅲ 「基本的立場」の対立における実質的争点
Ⅳ 「基本的見解」の対立がもたらす「管轄権」の競合・抵触に対する国際法上の評価
Ⅴ 結 び
◆9 新たな軌道上の活動に対する管轄権問題の軽減可能性―宇宙からの「打上げ」を題材として〔青木節子〕
Ⅰ 問題の所在
Ⅱ 宇宙物体に対する管轄権行使の現状
Ⅲ 宇宙からの宇宙物体「打上げ」の登録実行
Ⅳ 結 論
◆10 国家承認制度と多数国間条約〔目賀田周一郎〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 未承認国への国際法の適用と残された問題
Ⅲ 日本における著作権保護に関するベルヌ条約の北朝鮮への適用問題
Ⅳ 多数国間条約におけるイスラエルとアラブ諸国の関係
Ⅴ 多数国間条約へのパレスチナの加入の動き
Ⅵ 国際紛争平和的処理条約へのパレスチナとコソボの加入問題
Ⅶ 人種差別撤廃条約に基づくパレスチナの国家間通報手続
Ⅷ パレスチナ占領地におけるICC規程の適用問題
Ⅸ 米国大使館エルサレム移転問題
Ⅹ 論点の整理
Ⅺ おわりに
◆11 国家実行から見る政府承認の再考察〔大平真嗣〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 政府承認と諸外国の国家実行
Ⅲ 日本の国家実行と伝統的な政府承認
Ⅳ 「政府承認の回避ないし廃止」と「伝統的な政府承認」に関する考察
Ⅴ おわりに
◆12 不承認主義に基づく認定の法的効果に関する一考察―不承認義務と国際法上の協力義務の関係を踏まえて〔雨野 統〕
Ⅰ 問題の所在
Ⅱ 不承認主義の国際法上の位置づけ
Ⅲ 国際判例における不承認義務の位置づけ
Ⅳ 結 語
◆Ⅲ◆ 国際立法
◆13 留保禁止条約に付された留保相当解釈宣言の法的効果―「条約の留保に関する実行ガイド」を手がかりに〔浅田正彦〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ トラテロルコ条約,追加議定書Ⅱおよび核兵器国による宣言
Ⅲ 「条約の留保に関する実行ガイド」(実行ガイド)における留保と解釈宣言
Ⅳ 留保禁止条約に付された留保の法的効果
Ⅴ トラテロルコ議定書に付された「条件としての解釈宣言」の法的効果
Ⅵ おわりに
◆14 国際法委員会の作業に関する批判的考察―強行規範に関する結論草案を中心に〔村瀬信也〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 強行規範に関する結論草案
Ⅲ 法の一般原則に関する結論草案
Ⅳ ロシアのウクライナ侵略と関連議題
Ⅴ 結びに代えて
◆15 岐路に立つ国家責任条文―総会第6委員会における最終形態をめぐる攻防〔薬師寺公夫〕
Ⅰ 問題の所在―国家責任条文に何が起こっているのか
Ⅱ 国家責任条文の最終形態をめぐる総会決議の到達点と問題解決の模索
Ⅲ 国家責任条文の法的地位と国際裁判所等による援用の意味
Ⅳ むすびにかえて―問題解決に向けて
◆Ⅳ◆ 国際組織と国際協力
◆16 国際組織に関するILCの起草作業に関する一考察―「国際組織が当事者である紛争の解決」に関する作業を素材として〔植木俊哉〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 「国際組織が当事者である紛争の解決」に関する起草作業の開始
Ⅲ 起草する「法形式」に関する選択―「ガイドライン草案」(draft gui deli ne)
Ⅳ 「国際組織」の定義と要件をめぐる再論
Ⅴ 「国際組織が当事者である紛争」の解決手続をめぐる問題
Ⅵ おわりに―本議題に関するILCの作業の理論的意義
◆17 国際行政連合・再考―「協力の国際法」の起点として〔山田哲也〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 電信機の発明・実用化と国際化―国際郵便との対比
Ⅲ 国際法の構造変化論と国際行政連合
Ⅳ むすびにかえて
◆18 政治犯不引渡原則の再評価―欧州逮捕状に基づくカタルーニャ分離独立派の身柄請求を手掛かりとして〔洪 恵子〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ プッチダモンの引渡しに関する事件の概要
Ⅲ 欧州逮捕状(制度)の概要と特徴
Ⅳ 犯罪の政治性と欧州逮捕状制度
Ⅴ おわりに
◆19 文化多様性条約における規範の多重性の意義―条約採択から20年を迎えるにあたって〔小寺智史〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 文化多様性条約における規範の多重性
Ⅲ 特恵待遇の実施状況
Ⅳ フェア・カルチャーと特恵待遇
Ⅴ おわりに
◆20 ヨーロッパにおける裁判官の独立―裁判官対話によるヨーロッパ基準の生成〔須網隆夫〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 欧州人権裁判所と「裁判官の独立」
Ⅲ EU司法裁判所と「裁判官の独立」
Ⅳ 裁判官対話による基準の形成―「司法評議会の独立」と「裁判官の独立」
Ⅴ 結語―国際裁判所裁判官の独立への視点
◆Ⅴ◆ 人 権
◆21 国連人権条約機関における国家報告制度の運用実務―自由権規約委員会を例に〔寺谷広司〕
Ⅰ 序 問題の所在
Ⅱ 審議手続サイクルの実際
Ⅲ 制度運営の基盤―審査参加者と成果物の法的性格
Ⅳ 結 び
◆22 中国人権外交の転換―人権分野における「相互に有益な協力」概念をめぐって〔坂元茂樹〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 人権観念の対立は本当に存在するのか
Ⅲ 国連人権理事会における普遍的定期審査の機能
Ⅳ 中国主導による「相互に有益な協力」の概念の展開
Ⅴ おわりに
◆23 「ビジネスと人権」と労働―人権法の中での労働権の主流化〔吾郷眞一〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 「ビジネスと人権」の規範性
Ⅲ UNGPの中での労働の地位
Ⅳ 労働権と人権
Ⅴ 2022年ILO条約勧告適用専門家委員会と人権条約機構との対話開始の意義
Ⅵ ILOと国連との協働による相乗効果
Ⅶ おわりに
◆24 欧州人権条約第3条の違法性審査における人間の尊厳概念の役割―欧州人権裁判所2015年9月28日大法廷判決Bouyid対ベルギー〔小坂田裕子〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 事実概要と小法廷判決
Ⅲ 大法廷判決と共同反対意見
Ⅳ Bouyid事件大法廷判決の意義
Ⅴ おわりに
◆25 庇護の外部化と国際人権・難民法〔北村泰三〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 難民条約の場所的適用範囲
Ⅲ 安全な第三国(STC)概念に基づく庇護の外部化
Ⅳ むすびに―庇護の外部化の位置づけ
◆26 自由権規約委員会の同性婚勧告に関する一考察〔谷口洋幸〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 自由権規約委員会の同性婚勧告
Ⅲ 同性婚勧告に至る経緯
Ⅳ 同性婚勧告を取り巻く現状
Ⅴ 同性婚勧告の意義
Ⅵ おわりに
◆Ⅵ◆ 紛争解決
◆27 国際法学の実務と理論における学際性―国際裁判を素材に〔竹内雅俊〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 国際法学の「学際的なアプローチ」の展開と批判
Ⅲ 協働に関するいくつかのモデル
Ⅳ 実務における2種類の協働の方法論
Ⅴ 結びに代えて
◆28 同一紛争処理制度下で争点が共通する複数事案が同時並行して進行する場合の法的課題〔小林友彦〕
Ⅰ はじめに:問題意識
Ⅱ 紛争の経緯
Ⅲ 安全保障例外に関する両パネル判断の特徴
Ⅳ いくつかの論点の分析
Ⅴ 結 論
◆29 国際司法裁判所における貨幣用金原則の再構成〔山形英郎〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 貨幣用金原則の適用要件
Ⅲ 「並行的」紛争処理と「前提的」紛争処理
Ⅳ 「前提的紛争処理」の態様:「潜在的問題」
Ⅴ おわりに
◆30 投資条約における択一規定(fork in the road provision)と条約仲裁廷の管轄権〔森川俊孝〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 択一規定の内容と問題の所在
Ⅲ 投資条約仲裁廷による択一規定の解釈と課題
Ⅳ おわりに
◆31 国際裁判におけるオンライン審理手続〔中島 啓〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ コロナ禍におけるオンライン審理方式の整備と運用
Ⅲ 対面方式とオンライン方式の相違
Ⅳ おわりに
◆Ⅶ◆ 安全保障
◆32 国連平和協力法案―安全保障法制の原点〔堀之内秀久〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ イラクのクウェート侵攻と国際社会の反応
Ⅲ 我が国内の議論
Ⅳ 中東貢献策
Ⅴ 国連平和協力法案
Ⅵ 蹉跌からの出発
Ⅶ おわりに
◆33 集団的自衛権のジレンマ―NATOとウクライナ戦争〔三上正裕〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 集団的自衛権の両面性
Ⅲ NATOの集団防衛の構造
Ⅳ NATOの誕生と批判・反論
Ⅴ 非5条・危機管理活動の拡大
Ⅵ ロシアによるウクライナ侵略
Ⅶ ウクライナ侵略に対するNATOの対応
Ⅷ おわりに
◆34 日本の新安全保障法制の抑制性による国際法抵触という逆説的局面―集団的自衛権の行使形態論に触れつつ〔真山 全〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 自衛隊と外国軍の協同の評価問題
Ⅲ 新安全保障法制から生じる問題
Ⅳ 旧来の国内法に伏在していた問題の顕在化
Ⅴ おわりに
◆35 パレスチナに関するICJ勧告的意見手続きにおける日本の陳述(報告)〔御巫智洋〕
Ⅰ はじめに
Ⅱ 2023年7月提出の陳述書
Ⅲ 2024年2月22日の口頭陳述
Ⅳ おわりに