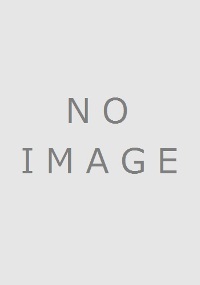尊厳の平等という未来へ
出版社: 信山社出版
- 「人は誰も差別や暴力や偏見によって貶められてはならない」。ジェンダー平等社会に必要なものは。未来への願いをこめた熱き提言。
- 「人は誰も差別や暴力や偏見によって貶められてはならない」。ジェンダー平等社会に必要なものは。未来への願いをこめた熱き提言。
- ◆個人の尊厳が保障される社会を求めて◆
「人は誰も差別や暴力や偏見によって貶められてはならない」。民主主義の弱体化、武力紛争やデジタル技術を用いた権利侵害や女性への暴力が、いま全世界に広がっている中で、これらに抗するジェンダー平等社会に必要なものは何か。未来への願いをこめた著者からの熱き提言。 - 『尊厳の平等という未来へ』(学術選書)
浅倉むつ子(早稲田大学名誉教授 東京都立大学名誉教授)
【目 次】
・はしがき
◆第1章◆包括的差別禁止法制と複合差別
◆1 包括的差別禁止立法の検討課題
Ⅰ はじめに
Ⅱ 雇用差別をめぐる現行法制の概要
Ⅲ 国際社会からの要請―包括的差別禁止法制へ
1 ILO111号条約批准という要請/2 女性差別撤廃委員会による「総括所見」/3 国際社会からの要請に応えるために
Ⅳ 包括的差別禁止法制にあたり検討すべきこと
1 差別の反規範性/2 差別禁止法制の目的/3 禁止されるべき差別事由/4 禁止される差別類型/5 差別禁止法制の実効性確保
◆2 雇用平等の展望と包括的差別禁止法
Ⅰ はじめに
Ⅱ 雇用平等はなぜ重要なのか
Ⅲ ジェンダー平等を阻害する要因
Ⅳ 雇用差別関連法制の現状
1 国際社会からの指摘/2 雇用差別をめぐる現行法制の概要
Ⅴ 包括的差別禁止立法の意義
◆3 性差別禁止法のエンフォースメント
Ⅰ 雇用差別禁止法制の整備・充実という要請
Ⅱ 禁止される差別事由の拡大傾向
Ⅲ 禁止される差別行為類型は拡大しているか
Ⅳ 差別禁止法制のエンフォースメント
◆4 イギリス平等法における複合差別禁止規定
Ⅰ はじめに
Ⅱ 差別禁止立法の3つのモデル
Ⅲ 複合差別のさまざまな態様
Ⅳ Bahl事件判決
1 事実の概要/2 ETの判断/3 上訴審の判断
Ⅴ 2010年平等法と結合差別
1 2010年平等法の制定/2 2010年平等法14条の意味/3 2010年平等法14条の限界
Ⅵ MoD事件判決
1 事実の概要/2 ETの判断/3 EATの判断/4 評価
Ⅶ おわりに
◆5 障害を理由とする雇用差別の禁止
Ⅰ はじめに
Ⅱ 雇用差別禁止法制の全般的現状
1 禁止されるべき差別事由の3類型/2 現行法の状況
Ⅲ 障害をめぐる差別禁止法制と雇用
1 障害者基本法(2011年改正)/2 障害者差別解消法(2013年制定)/3 障害者雇用促進法(2013年改正)
Ⅳ 障害者雇用促進法の意義と課題
1 障害者雇用をめぐる2つのアプローチ/2 禁止される差別概念―「直接差別」のみの禁止という特色/3 差別と合理的配慮義務不履行の関係性/4 差別禁止規定違反に対する法的効果について
Ⅴ 障害差別における残された問題
1 雇用率制度/2 特例子会社/3 最低賃金制度の特例/4 通勤支援
◆6 女性差別と障害差別の交差性を考える
Ⅰ はじめに
Ⅱ 国際人権文書にみる障害女性の位置づけ
1 フェミニズム理論の展開と差別の交差性の告発/2 国際人権文書にみるマイノリティ女性への関心/3 女性差別撤廃条約と障害女性/4 障害学の展開とフェミニズム理論/5 障害者権利条約にみる交差差別と複合差別概念
Ⅲ 日本の法規定と障害女性の権利
1 条約批准に伴う法制度改正/2 2021年の障害者差別解消法の改正
Ⅳ 障害者権利条約は国内で遵守されているか
1 障害者権利委員会への日本政府報告/2 権利条約の締約国の義務/3 性と生殖に関する権利について
Ⅴ おわりに
◆第2章◆均等法をめぐる攻防
◆7 均等法の立法史
Ⅰ はじめに
Ⅱ 前 史
1 先行した裁判/2 国際的動向/3 男女別雇用管理の実態
Ⅲ 均等法の制定過程
1 野党各党の法案/2 労使の攻防―婦人少年問題審議会「建議」の三論併記/3 法形式をめぐる内情/4 国会における審議/5 施行に向けて
Ⅳ 「福祉法」としての1985年均等法
1 1985年法の構成と特色/2 労基法改正/3 1986年施行後に生じたこと
Ⅴ 均等法の展開過程(その1)―1997年第1回目の法改正
1 均等法施行後の社会・経済的背景/2 1997年改正に至る経緯/3 1997年改正均等法/4 一般女性保護規定の廃止に伴う法改正/5 97年改正法の施行と裁判への影響
Ⅵ 均等法の展開過程(その2)―2006年第2回目の法改正
1 改正に至る経緯/2 2006年改正均等法/3 附帯決議等
Ⅶ 均等法の現在
1 その後の改正動向/2 女性活躍推進法の制定
Ⅷ おわりに
◆8 労働組合運動と女性の要求
Ⅰ はじめに―「二つの敵対者」
Ⅱ 男女差別に気づく
Ⅲ 雇用平等法を求めて―女性たちの連帯と共闘の経験
Ⅳ 雇用平等法と均等法の落差
1 求めていた雇用平等法とは違った法律/2 均等法制定過程における攻防/3 持てる力は出し切った
Ⅴ 一般女性保護規定廃止をめぐる苦悩
Ⅵ 「男女共通規制」という方針―男女ともに人間らしい労働と生活を
1 一般女性保護規定の廃止と激変緩和措置/2 「男女共通規制」方針の登場
Ⅶ 私たちの手に「生活」を取り戻そう
1 「働き方改革法」―労働時間短縮政策の貧困/2 生活時間アプローチ/3 男女共通規制と生活時間アプローチ
Ⅷ おわりに―労働運動の未来を描く夢
1 男性も女性も,正規も非正規も/2 よりよい社会を創造する「共存関係」をめざして
◆第3章◆男女賃金差別の是正・解消
◆9 ジェンダー視点からみた同一価値労働同一賃金原則の課題
Ⅰ はじめに
Ⅱ 国際基準としての男女「同一価値労働同一賃金」原則
Ⅲ 男女賃金差別裁判の40年
1 明白な制度的差別事案/2 職務の価値評価が問題となる事案/3 男女別コース事案/4 職能資格給における査定差別/5 解決されるべき課題
Ⅳ 非正規労働者差別裁判の20年
1 パート労働法旧8条/2 労働契約法20条/3 パート労働法8条
Ⅴ 安倍政権による「同一労働同一賃金」スローガン
Ⅵ 日本で「同一価値労働同一賃金」を実施するために
◆10 同一価値労働同一賃金を実現する法制度の提案―賃金格差是正のプロアクティブモデルをめざして
Ⅰ はじめに
Ⅱ 日本の現行法―男女間および正規・非正規間の賃金平等規定
1 実体法とその履行確保手段/2 男女間の賃金平等規定/3 正規・非正規間の賃金平等規定
Ⅲ カナダのペイ・エクイティ法制
1 なぜカナダに注目するのか/2 重層的な男女賃金平等法制/3 オンタリオ州のペイ・エクイティ法
Ⅳ 同一価値労働同一賃金を実現する法制度の提案
1 同一価値労働同一賃金原則の明文化/2 賃金格差是正のプロアクティブモデルをめざして
Ⅴ おわりに
◆11 男女間賃金格差是正に取り組む法の構想を
Ⅰ はじめに―10年前の共編著
Ⅱ 賃金格差をめぐる国内の動向
1 非正規労働と「同一労働同一賃金」/2 男女賃金格差をめぐって―ILOと国連からの勧告
Ⅲ 男女賃金格差をめぐる国際的動向
1 イコール・ペイ・デイ(男女同一賃金の日)/2 各国の賃金透明化法など
Ⅳ 新たな共同研究
1 プロアクティブな賃金格差是正立法への関心/2 前提としてふまえておくべきこと/3 賃金格差是正のためのプロアクティブモデルの提案
◆12 女性活躍推進法における男女賃金格差開示義務
Ⅰ 男女賃金格差の実情
Ⅱ 賃金透明化に関する近年の国際動向
Ⅲ 「男女の賃金の差異」情報開示決定に至る経緯
1 国会における質疑/2 新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計/3 労働政策審議会雇用環境・均等分科会における議論
Ⅳ 女性活躍推進法における男女の賃金の差異をめぐる公表義務について
1 女性活躍推進法の規定/2 省令・指針の改正,通達の発出
Ⅴ 若干の評価
Ⅵ 男女賃金格差の縮小・是正のために
1 「男女の賃金の差異」の開示をどう利用するのか/2 将来の立法構想に向けて
◆第4章 ジェンダー視点による「働き方改革」批判
◆13 雇用分野のジェンダー不平等はなぜ解消されないのか
Ⅰ はじめに
Ⅱ 雇用におけるジェンダー不平等の主な要因
Ⅲ 労働法制はジェンダー不平等解消に効果的か
Ⅳ ジェンダー不平等をめぐる判例法理の到達点
1 明白な性差別的制度からコース別雇用へ/2 妊娠・出産・育児と不利益取扱い/3 中国電力事件
Ⅴ おわりに
◆14 労働時間法制のあり方を考える―生活者の視点から
Ⅰ 労働時間を規制する目的
Ⅱ 長時間労働の常態化と労働者の健康危機
Ⅲ 労働時間政策の経緯
1 労働基準法改正の経緯/2 総量的実労働時間短縮政策の放棄
Ⅳ 「高度プロフェッショナル制度」の問題性
Ⅴ 労働時間法制のあり方を考える
1 「ケアレス・マン」モデルの見直し/2 生活時間アプローチへ
◆15 なんのための労働時間短縮なのか
Ⅰ 労働時間を規制する根拠
Ⅱ 日本の労働時間政策
Ⅲ 労働時間規制立法の類型
Ⅳ 長時間労働の実態
Ⅴ 「働き方改革」における上限規制の論拠
Ⅵ 「生活時間を取り戻す」ために
Ⅶ 生活時間アプローチの基本コンセプト
◆16 「働き方改革」は待遇格差を是正できるか
Ⅰ 安倍政権による「同一労働同一賃金」政策
Ⅱ 示された「ガイドライン案」
Ⅲ どのように評価すべきか?
Ⅳ 職務評価の実践
Ⅴ 法改正の展望
◆17 安倍政権の労働法制「改革」を批判する
Ⅰ 経済政策は成功しているのか
Ⅱ 男女平等に無理解な女性政策
Ⅲ 経済政策に劣後する理念なき労働政策
Ⅳ 「スピード感」とは拙速ということか
Ⅴ 「法案要綱」にメリットはない
1 「同一労働同一賃金」/2 労働時間短縮のために
◆18 ジェンダー視点で読み解く労働判例
Ⅰ ジェンダー関連の労働立法の変遷
1 差別と格差の規制/2 WLBをめざす法/3 ハラスメント関連法
Ⅱ 判例法理の到達点
1 時間外労働と配転をめぐる判例法理/2 男女賃金差別をめぐる判例法理/3 非正規労働者の処遇格差をめぐる判例法理/4 母性保護や育児休業等を理由とする不利益取扱い/5 ハラスメントをめぐる判例法理
Ⅲ 今後の検討課題―ケア労働を展望する裁判
◆第5章◆コロナ禍と労働法
◆19 新型コロナとジェンダー
Ⅰ はじめに
Ⅱ 国際機関からの提言
Ⅲ 女性・女児に対するコロナ禍の影響
Ⅳ 日本の新型コロナ対策―ジェンダー視点の欠如
1 見直されなかった「世帯主義」/2 女性支援を阻んでいる法制度/3 非正規公務員問題
◆20 コロナ禍におけるジェンダー問題
Ⅰ はじめに
Ⅱ ジェンダー視点による対策―スタート時点での遅れ
Ⅲ コロナ禍によって何がおきたのか
1 雇用動向の変化/2 エッセンシャル・ワーカーの困難/3 私生活上の危険と困難の増大
Ⅳ 主要な緊急対応策
Ⅴ 内閣府のコロナ対策
1 第5次男女共同参画基本計画/2 「研究会報告書」と「重点方針2021」
Ⅵ ポストコロナの社会で重要なこと
1 「ケアレス・マン」から脱却する必要/2 改革から遠い現実―法制度と司法判断
Ⅶ おわりに―日本の人権を国際基準に
◆21 ジェンダーをめぐる課題と法律家の役割
Ⅰ はじめに
Ⅱ 新型コロナ禍と世界的価値観の変化
Ⅲ ジェンダー平等の視点からみた日本の労働政策の課題
1 新型コロナ緊急経済対策の失敗/2 労働分野のジェンダー格差と「ケアレス・マン」モデル/3 労働時間短縮と賃金平等の新しい考え方
Ⅳ 法律家の役割―ケア労働をめぐる訴訟を契機に
1 場当たり的な弥縫策から包括的な法政策へ/2 女性の権利を国際基準に/3 ケア労働をめぐる訴訟を例として
◆第6章◆男女共同参画条例
◆22 多摩市の条例策定への道のり
Ⅰ はじめに
Ⅱ 男女共同参画条例とジェンダー法―個人的経験も交えて
Ⅲ 多摩市条例の制定過程
1 革新市政の誕生と条例策定方針/2 条例「懇談会」での検討の経緯/3 条例が採択されるまで
Ⅳ 多摩市で条例ができた理由
1 多摩市条例の特色/2 条例を成立させた背景
Ⅴ おわりに
◆23 男女共同参画条例に基づく「苦情処理」の意義
Ⅰ はじめに
Ⅱ 男女共同参画社会基本法
1 男女平等原則の段階的展開/2 「基本法」の意義と男女共同参画の現状/3 国の施策に関する苦情等の事例
Ⅲ 東京都条例と埼玉県条例の比較
1 「基本法」以後の地方条例の動向/2 条例の策定過程/3 条例の内容比較/4 苦情処理制度の有無
Ⅳ 埼玉県条例における苦情処理の実態
1 苦情処理委員会の仕組み/2 苦情処理事案取扱いの概要
Ⅴ 多摩市条例について
1 東京都下の区市町村条例/2 多摩市の条例ができるまで/3 多摩市条例の内容上の特色
Ⅴ おわりに
◆第7章◆女性差別撤廃条約の実効性
◆24 女性差別撤廃条約批准後の国内法の展開
Ⅰ はじめに
Ⅱ 条約の批准と国内法改正
Ⅲ CEDAWによる国家報告制度と総括所見
Ⅳ 条約の批准から男女共同参画社会基本法まで(1985年~1999年)
1 雇用分野の法改正/2 男女共同参画社会基本法の制定
Ⅴ ジェンダーをめぐる対立構造の鮮明化(2000年~2009年まで)
1 ジェンダー・フリーへのバックラッシュの台頭/2 DV防止法の制定と改正/3 雇用分野の法改正―均等法とパート労働法
Ⅵ 最近10年間の法改正の動向(2010年~今日まで)
1 家族法改正の行方/2 刑法の性暴力規定の改定/3 政治分野の候補者男女均等法
Ⅶ おわりに―残されている課題
◆25 女性差別撤廃条約に言及する国内判例の分析
Ⅰ はじめに
Ⅱ 「条約の規定が言及された判例」が問われている意味
Ⅲ 判例の検索
Ⅳ 条約の「直接適用可能性」をめぐる判例動向
Ⅴ 労働事件と女性差別撤廃条約
Ⅵ 原告らが条約を援用して提訴した事案
Ⅶ おわりに
◆26 女性差別撤廃条約選択議定書―批准の「障害」とは何か
Ⅰ 女性差別撤廃条約の選択議定書
Ⅱ 批准の要請
Ⅲ 批准の期待が高まった民主党政権時代
Ⅳ その後の外務省
Ⅴ 外務省の研究会で明らかになっていること
Ⅵ 国会審議と地方議会の現状
Ⅶ おわりに
◆27 個人通報制度が変えるこの国の人権状況
Ⅰ 女性差別撤廃条約への大きな期待
Ⅱ 裁判所では条約は「絵に描いた餅」?
Ⅲ 選択議定書と個人通報制度
Ⅳ いくつかの個人通報事案
Ⅴ 委員会の「見解」を強制する仕組みはあるのか
Ⅵ 選択議定書を批准しない理由は何か
Ⅶ 加速している批准の要請
Ⅷ 司法を変え,人権状況を改善する
◆28 女性差別撤廃条約選択議定書の批准を求める地方議会意見書の動向
Ⅰ 全国114の地方議会が「意見書」を採択
Ⅱ 意見書採択動向と「実現アクション」によるアンケート調査
1 「実現アクション」参加団体/2 地方議会一覧/3 参加団体からの情報収集アンケート調査
Ⅲ 意見書の「名称」
Ⅳ 意見書の採択事情さまざま
1 意見書提案の契機/2 意見書採択の経緯/3 妥協点を見出すための調整
Ⅴ 審議過程で出た質問や反対意見
◆29 女性差別撤廃条約の個人通報事例―重度障害児の在宅介護と年金保険算定上の不利益
Ⅰ 事案の概要
Ⅱ 委員会の見解
1 受理可能性の判断/2 本案の検討/3 結論と勧告
Ⅲ 解 説
1 委員会による条約の解釈とその意義/2 残された課題/3 日本の現状と本件からの示唆
◆第8章◆ジェンダー主流化をめざす
◆30 「ジェンダー主流化」を国内法規範に
Ⅰ はじめに
Ⅱ 女性差別撤廃条約の国内適用をめぐる判例上の通説
Ⅲ 選択議定書批准の意義
Ⅳ 国際社会からの「ジェンダー主流化」要請と国内法における具体化
Ⅴ 安保関連法制定プロセスにおけるジェンダー主流化の侵害
Ⅵ おわりに
◆31 北京から25年:ジェンダー関連の国内法の展開と課題
Ⅰ はじめに
Ⅱ 北京行動綱領とジェンダー主流化
Ⅲ 基本法とDV防止法
Ⅳ 雇用分野の法
1 雇用平等/2 ワークライフバランス/3 各種ハラスメントの防止
Ⅴ 家族法
Ⅵ 刑法の性犯罪規定
Ⅶ 政治分野の候補者男女均等法
Ⅷ 「ジェンダー主流化」を実現する
◆32 性差別撤廃運動の新展開
Ⅰ はじめに
Ⅱ 日本における「保護と平等」論議の到達点
Ⅲ 差別撤廃の国際的展開
Ⅳ 暴力とハラスメント撤廃政策の到達点
◆33 性差別撤廃運動の35年―バックラッシュとの攻防
Ⅰ コロナ下で声をあげた「#わきまえない女」たち
Ⅱ 女性差別撤廃条約と男女共同参画社会基本法(1985~99年)
Ⅲ ジェンダーをめぐる対立構造の鮮明化(2000~11年)
Ⅳ 第2次安倍政権以降(2012年から今日まで)
◆第9章◆判例を契機に考える
◆34 職場における旧姓使用禁止は許されるか―学校法人日本大学第三学園事件(東京地裁平成28年10月11日判決・労働判例1150号5頁)
Ⅰ 事実の概要
Ⅱ 判 旨
Ⅲ 検 討
1 はじめに/2 判決の論理/3 職場における人格権をめぐる先例/4 職場における人格権と通称使用/5 通称使用禁止に合理性・必要性はあるか/6 おわりに
◆35 公務における「隠されたコース別人事」と性差別―東京地裁平成31年2月27日判決を契機として―
Ⅰ はじめに
Ⅱ 事実の概要
Ⅲ 判旨―請求棄却
Ⅳ 検 討
1 性差別禁止原則の下での任命権者裁量権限の逸脱・濫用判断枠組/2 男女格差の存在と性差別の推認/3 籍別人事の実情とその違法性/4 昇任の遅れの原因について
Ⅴ 結びに代えて
◆36 「ケア」を軽んじる社会に未来はあるか?―ジャパンビジネスラボ事件
Ⅰ はじめに
Ⅱ ジャパンビジネスラボ事件―事実の概要と判旨
1 事実の概要/2 2審判決(東京高裁令和元(2019)年11月28日判決・労働判例1215号5頁)
Ⅱ 判決の検討
1 「合意」の解釈とその有効性について/2 契約社員契約の更新の有無/3 XおよびYによる不法行為の有無
Ⅳ 本判決を契機に考える
1 育児休業からの原職復帰/2 Y企業の体質を問う/3 バックアップ体制の整備/4 ケアに満ちた社会を
◆第10章◆ハラスメントの防止と撤廃
◆37 セクシュアル・ハラスメントをめぐる法的課題
Ⅰ はじめに
Ⅱ 男女雇用機会均等法とセクシュアル・ハラスメント
1 ヴィンソン事件と福岡事件/2 事業主の措置義務/3 均等法の施行状況と被害者の要望
Ⅲ その他のハラスメント
1 マタニティ・ハラスメント(均等法11条の3)/2 ケア・ハラスメント(育児介護休業法25条)/3 パワー・ハラスメント(労働施策総合推進法30条の2)
Ⅳ 日本の法規定の特色
Ⅴ 民事訴訟の動向
1 加害者の責任/2 使用者の責任/3 懲戒処分/4 損害賠償額
Ⅵ 今後の立法政策を展望して
1 ILO第190号条約の要請/2 法改正の必要
◆38 ハラスメントの防止と撤廃をめざす法政策―ILO第190号条約のアプローチに学ぶ
Ⅰ はじめに
Ⅱ 条約と勧告の制定過程
1 ジェンダー平等とディーセントワーク/2 暴力とハラスメントをめぐる実態調査/3 2016年の専門家会合/4 2018年の第一次討議/5 2019年の第二次討議
Ⅲ 第190号条約と第206号勧告の主な内容
1 暴力とハラスメントの定義/2 規制の対象範囲/3 基本的アプローチ/4 労働の基本原則と権利/5 加盟国と使用者の採るべき措置/6 執行と救済
Ⅳ ILO条約批准に向けた国内法整備の課題
1 ILO条約の発効/2 国内法規制の現状と特色/3 ILO条約批准に向けて
◆39 ハラスメント根絶と学術の発展―改めて京大・矢野事件を考える
Ⅰ はじめに
Ⅱ 京大・矢野事件とは
1 事件が投げかけた衝撃/2 事実の概要/3 裁判の結末/4 特筆すべき判断
Ⅲ 大学組織とハラスメント
1 大学の構造的な問題/2 ハラスメント対策の進展/3 大学におけるハラスメント紛争の傾向
Ⅳ 学術の質を高めるために
1 ブタペスト宣言/2 社会政策学会のハラスメント調査をみる
◆40 大学におけるセクシュアル・ハラスメント判例総覧50件
Ⅰ はじめに
Ⅱ 大学におけるセクハラ対策と法規制
Ⅲ 大学におけるセクハラ裁判例50件の4分類
Ⅳ セクシュアル・ハラスメントの行為類型
Ⅴ セクシュアル・ハラスメントの成否
1 供述の信用性/2 同意の有無
Ⅵ 大学の対応の是非
1 被害者(院生・学生)からの訴え(Ⅱ型)/2 加害者とされる教員・職員からの訴え(Ⅰ型)/3 その他(Ⅳ型)
◆第11章◆研究・教育・学術
◆41 労働法の「女性中心アプローチ」
Ⅰ はじめに
Ⅱ 婦人労働問題研究から出発―オリジナリティを模索した時代
1 東京都立大学法学部の学生時代(1967年~ )/2 大学院修士課程から博士課程へ(1971年~)
Ⅲ 雇用平等法理の日英比較―一つの理論的支柱
Ⅳ 「フェミニズム法学」と「労働法のジェンダー分析」
1 アメリカで出会ったフェミニズム法学/2 「労働法のジェンダー分析」
Ⅴ 労働法の「女性中心アプローチ」
Ⅵ ジェンダー法との架橋を求めて
1 時代の変化の中で/2 包括的差別禁止立法の研究/3 「男女共通規制」と生活時間プロジェクト
Ⅶ おわりに
◆42 ジェンダー法教育の意義と課題―早稲田大学ロースクールの経験を中心に
Ⅰ はじめに
Ⅱ 「ジェンダー法関連科目」の全国的開講状況―2つの調査から
Ⅲ 早稲田大学ロースクールの経験から
1 ジェンダー法関連カリキュラム概要/2 講義「ジェンダーと法」―特色と課題
Ⅳ おわりに
◆43 日本学術会議会員の任命拒否事件の本質
Ⅰ はじめに
Ⅱ 何が起きたのか
Ⅲ 任命拒否の違憲性・違法性
Ⅳ 任命拒否に「正当理由」はあるのか
Ⅴ 任命拒否の本当の理由
Ⅵ 学術会議の設置形態をめぐる議論
Ⅶ おわりに
◆44 学術会議の独立性を毀損してはならない
Ⅰ はじめに
Ⅱ 任命拒否とその後の経緯
Ⅲ 現段階―内閣府「方針」への学術会議からの懸念表明
Ⅳ 改めて,任命拒否の違法性・違憲性を問う
Ⅴ 任命拒否の本当の理由
Ⅵ おわりに