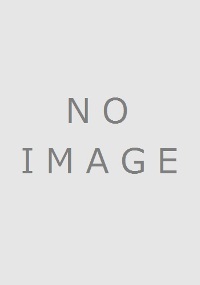著作権法はどこで間違えたのか
出版社: 信山社出版
- 生成AIによる学習は、「公正な利用」か。生成AIによる作品は、創作的な表現か。生成AIによる作品の「著作者」は誰か。
- 生成AIによる学習は、「公正な利用」か。生成AIによる作品は、創作的な表現か。生成AIによる作品の「著作者」は誰か。
- ◆独自の学説を創作し続けてきた民法学者が、創作の実践者として現行の著作権法に向き合った本◆
生成AIによる学習は、「公正な利用」か。生成AIによる作品は、創作的な表現か。生成AIによる作品の「著作者」は誰か。自らの創作体験に基づく「文化的所産の利用サイクル」という実践モデルに基づいて、現行の著作権法とその学説を検証、著作権法の改正への方向性を示す。 - 『著作権法はどこで間違えたのか ―「文化的所産の利用サイクル」説の観点から』
加賀山茂(名古屋大学名誉教授、明治学院大学名誉教授)著
【目 次】
はしがき
◆はじめに
1 生成AI開発者がノーベル賞を受賞したことの驚きと不安
2 本書の目的と特色
3 著作権法のシンプルでわかりやすい構造を目指して
◆第1部◆著作権法はどこを間違えているのか
◆第1章 著作物を無体物に限定したことの誤り
第1節 旧法から現行法へ移行する過渡期の学説(山本桂一説)
第2節 現行著作権法の通説の考え方(上野達弘説)
第3節 新しい著作権学説による著作物の考え方
◆第2章 創作できるのは人間だけであるとの思い込み
第1節 生成AIの出現の衝撃
第2節 人間だけが有する能力とされてきた自然言語を操る生成AI
第3節 自然言語で指令すると生成AIは絵画も作成できる
第4節 人間とAIが協力して文化を発展させる時代の到来
第5節 生成AIの作品の著作者が生成AIのユーザとなるための条件
◆第3章 著作権を所有権と対比して異同を探求したことの誤り
第1節 旧法から現行法へ移行する過渡期の学説(山本桂一説)
第2節 現行著作権法の通説の考え方(中山信弘説)
第3節 新しい著作権学説による著作物,および,著作権の考え方
◆第4章 著作権侵害の定義なしに「依拠」を制裁するという誤り
第1節 「権利侵害」の定義なしで制裁を加える著作権法の異常
第2節 著作権法の罰則規定は罪刑法定主義に反している
第3節 著作権法に置かれている過酷な刑罰規定の実態
◆第5章 著作権法が文化の発展を阻害するという誤り
第1節 世界に例を見ない著作者人格権の過保護
第2節 文化の発展を阻害する差止請求の誤り
第3節 判例百選事件の当事者は誰も悪くない,悪いのは著作物の差止制度
◆第2部◆著作権法はどこから間違い始めたのか
◆第6章 著作権法の間違いの軌跡
第1節 民法の物権法からの決別
第2節 著作から享受に至るプロセスの軽視
第3節 著作権侵害における民法の不法行為法への依存
◆第7章 著作権法の間違いに対する認識の変化と諦め
第1節 著作権法は,市民にとって理解が困難なまま放置されている
第2節 生成AIの出現による著作権法のさらなる混迷
第3節 著作権法学が立ち返るべき原点としての山本桂一説
◆第8章 公正な利用についての検討の放置
第1節 著作権法第1条の「公正な利用」の位置づけ
第2節 (一次的)著作における文化的所産の「公正な利用」
第3節 二次的著作における著作物の「公正な利用」
◆第3部◆著作権法はどうすれば間違いを正せるのか
◆第9章 物権法との再連携(動産上の制限物権としての著作権)
◆第10章 出版権,著作隣接権の著作権への統合による簡素化
◆第11章 著作権法の中核概念に関する改正案の提案
第1節 著作権法1条(目的)の改正案
第2節 公正な利用(著作権法1条)の定義と改正案
第3節 創作的表現(著作権法2条1項1号)の定義と改正案
第4節 著作者(著作権法2条1項2号)の再定義と改正案
第5節 著作権侵害(著作権法112条以下)の定義と改正案
◆結 論
1 著作権法の世界―文化的所産の利用サイクル
2 著作―思想又は感情の創作的表現
3 著作物―著作の固定化,それを通じた著作の再現と享受
4 著作権―著作物の上の所有権を「公正な利用」に制限する制限物権
5 フェア・ユース―「公正な利用」の判断基準
6 著作権侵害―著作物の不公正な利用
7 制裁よりも補償―文化の発展は依拠に始まる
◇おわりに
1 私の従来の専門分野(民法,消費者法,法情報学,法と経営学)
2 私と著作権法とのかかわり
3 謝 辞
・参照文献
・索 引