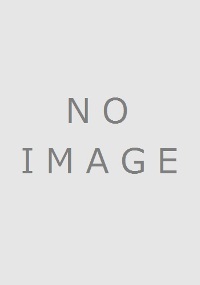フランス民法の伝統と革新 Ⅱ
出版社: 信山社出版
- 2世紀あまりのフランス民法典の歴史と伝統から、民法という社会の共存のルールの、現在及び将来のあり方を伝える。待望の第Ⅱ巻。
- 2世紀あまりのフランス民法典の歴史と伝統から、民法という社会の共存のルールの、現在及び将来のあり方を伝える。待望の第Ⅱ巻。
- ◆フランス民法の伝統と現代的潮流の理解に好適な書、待望の第Ⅱ巻(全2巻)◆
ピエール・クロック(Pierre Crocqː元パリ・パンテオン・アサス大学(パリ第2 大学))教授による日本人に向けた講演を、分かり易く構成し、1冊にまとめる。2世紀あまりのフランス民法典の歴史と伝統から、民法という社会の共存のルールの、現在及び将来のあり方を日本の読者に伝える。本第Ⅱ巻は【第Ⅰ部 担保一般】、【第Ⅱ部 保証】、【第Ⅲ部 その他】として、日本においても広く有益、かつ示唆に富む内容をまとめる。 - 『フランス民法の伝統と革新 Ⅱ― 担保とその周辺』
ピエール・クロック 著
大村敦志・野沢正充 監訳
【目 次】
・はしがき/大村敦志
◆第Ⅰ部 担保一般◆
◆1 フランス担保法の新たな展開―20世紀末と21世紀初頭における担保法の展開〔野澤正充訳〕
は じ め に
Ⅰ 諸原則の展開
A 附従性の原則に対する例外
B 適合性の原則の展開
Ⅱ 担保権の新たな区別
A 優先弁済性の区別
B 個人と事業者の区別
◆2 2006年3月23日のオルドナンス第346号による担保法の改正―成功か失敗か?〔野澤正充訳〕
Ⅰ 担保法へのアクセスの向上
A 担保法の構造における改良
B 担保法の内容の明確性
Ⅱ 物的担保の魅力的な改良
A 物的担保の設定の緩和
B 物的担保の実効性の向上
◆3 フランス法における設定者の担保価値維持義務〔片山直也訳〕
Ⅰ 流動資産担保(sûretés sur actifs circulants)において一般的に認められる義務
Ⅱ 担保目的財産の価格低下の場合に例外的に求められる義務
◆4 フランス法における担保執行者(agent des sûretés)〔野澤正充訳〕
は じ め に
Ⅰ 担保執行者は、特殊な受託者である
A 特殊な受託者の地位の正当性
B 特殊な受託者とすることの帰結
Ⅱ 担保の保有者の資格と被担保債権の保有者の分離
A 担保法制度と資格の分離との両立可能性
B 担保法制度における資格の分離の帰結
◆5 所有権担保と2017年フランス担保法改正準備草案〔片山直也訳〕
Ⅰ 所有権担保と担保の附従性の強化
A 所有権留保と「従物は主物に従う」準則の尊重
B 所有権留保とすべての不当な利得の禁止の尊重
Ⅱ 所有権担保と当事者の権限の増大
A 当事者の選択の自由の強化
B 当事者の処分権限の強化
◆6 フランス担保法改正とグローバル化〔今尾真・蛯原健介・黒田美亜紀訳〕
Ⅰ 法のグローバル化という外からの働きかけに直面したフランス法の改正
Ⅱ 担保法のグローバル化の要因としてのフランス法の改正
◆第Ⅱ部 保 証◆
◆7 フランス法における保証人に対する情報提供―近時の状況及び将来の改革の展望〔平野裕之訳〕
序 論
Ⅰ 〔保証〕契約締結に際する保証人に対する情報提供
A 主たる債務者の支払能力についての情報提供
B 保証人へのその〔保証〕契約の結果についての情報提供
Ⅱ 〔保証〕契約の履行に際しての保証人への情報提供
A 〔保証人になっていることを〕忘れてしまうことに対する保護
B 〔主たる債務者の不履行を保証人が〕知らないことに対する保護
◆8 21世紀初頭のフランス法における保証の展開〔野澤正充訳〕
は じ め に
Ⅰ 保証人の保護の拡大
A 契約の締結―裁判官の評価権限を害して拡張される保証人の保護
B 契約の履行―家族にもその範囲が拡大した保証人の保護
Ⅱ 保証債務に特徴的な要素の否定
◆9 フランス法における保証と個人の過剰債務処理手続〔野澤正充訳〕
は じ め に
Ⅰ 自然人である保証人の過剰債務の防止における画一性
A 過剰な保証に対するサンクション
B 保証債務の重大性についての保証人に対する情報の提供
Ⅱ 自然人である保証人の過剰債務処理の画一化
A 会社の債務の保証人である会社の経営者に対する個人の過剰債務処理手続の開始
B 合名会社(société en nom collectif)の社員である保証人の排除
◆10 フランス法における保証と会社〔野澤正充訳〕
は じ め に
Ⅰ 保証人の保護における会社の存在の影響
A 債務超過に陥った会社の救済の必要性と会社経営者である保証人の保護の拡大
B 保証人である会社の特別な保護規定
Ⅱ 会社の組織変更が保証に及ぼす影響
A 会社の組織変更が保証契約の一般的要件に及ぼす影響件
B 保証人である会社の組織変更に関する特別な場合
◆第Ⅲ部 その他◆
◆11 フランス民法典への信託の導入〔平野裕之訳〕
序 論
Ⅰ 新たな信託の「財産」管理方法としての利用可能性は少ない
A 実際に[財産]管理信託を利用する方法
B [立法]作業の準備段階で考えられていた[財産]管理信託の特殊な利用に対する疑念
Ⅱ 新たな信託の担保としての利用可能性は少ない
A 担保という機能からは適切ではない規定の存在
B 担保の機能を持つ[信託のために必要な]法制度が欠けていること
結 語
◆12 近時のフランス法における資産(patrimoine)論の展開〔原 恵美訳〕
第1部 オーブリ=ローの理論―多くの例外を抱える原則
Ⅰ 法人格の存在と資産の存在
A 人のみが資産を有するということ
B あらゆる人が資産を有するということ
Ⅱ 資産の不可分性
第2部 資産の保持者に認められた積極財産分離のための新たな権限
Ⅰ 積極財産の不完全な分離の承認
Ⅱ 充当資産の承認による完全な分離の承認
◆13 フランス倒産手続における担保の処遇〔下村信江訳〕
は じ め に
Ⅰ 人的担保に対する倒産手続法の影響
A 保証の場合における人的担保の付従性に由来する影響
B 倒産手続の迅速な開始を促進する立法者意思に由来する影響
Ⅱ 物的担保に対する倒産手続法の影響
A 企業の更生を促進する意思に結びつけられる影響
B 排他的な地位を与える担保の抵抗
◆14 フランス法における債務法改正後の債権譲渡〔齋藤由起訳〕
Ⅰ 債務法改正に対するダイイ譲渡の影響
A 一般法上の新債権譲渡に対するダイイ譲渡の明白な影響
B 一般法上の新債権譲渡の機能に対するダイイ譲渡の潜在的な影響
Ⅱ ダイイ譲渡に対する債務法改正の影響
A 債務法改正によるダイイ譲渡に関する法制度の強化
B 将来債権に関する法制度上の新たな相違の出現
◆15 債務法改正後における契約の相互依存性〔野澤正充訳〕
はじめに
Ⅰ 債務法の改正と相互依存性の存在
A 債務法の改正と相互依存性の根拠
B 債務法の改正と相互依存性の基準
Ⅱ 債務法の改正と相互依存性の効果
A 改正によって明示的に認められた効果
B 改正によって定められなかった効果
◇あとがき/野澤正充
・仏語目次
・著者紹介/監訳者・訳者紹介