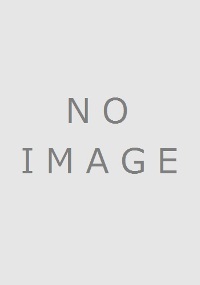不正義の克服
出版社: 明石書店
- 不正義が蔓延る現代社会。アマルティア・センは『正義のアイデア』で、ロールズの正義論を批判的に継承しながら、具体的なアイデアで不正義を解決するための方策を考えた。本書では、日本の文脈に即して、不正義を解決するための様々なアプローチを提示する。
- はじめに
序章 正義ヘのアプローチ
感情の重要性
公共的推論と理性
理由の複数性
情けは人のためならず
3人の子どもと1本の笛
客観性とそれぞれの立場
理論とアプローチの違い
先験的制度尊重主義の問題点
義務論と帰結主義の対立
制度・行為の正しさと実現された正義
グローバルな正義
第Ⅰ部 正義が求めるもの
第1章 客観性と理性の役割
賢明であることと正義
啓蒙主義の過信と粗雑な信念
アクバル皇帝と理性
止まった時計
アダム・スミスの「公平な観察者」
理性の及ぶ範囲
理性による精査と感情の役割
第2章 ロールズを超えて
センとロールズ
公正としての正義
ロールズの「正義の原理」
ロールズの基本財と自尊心の重要性
ロールズから学ぶべきこと
ロールズの問題点と課題
第3章 制度と個人
2つの立場
社会のあり方と制度
ガルブレイスの拮抗力
制度と帰結
制度と個人の相互依存性
第4章 社会的選択理論と弱者
アレクサンダー大王の会話
社会的選択理論の系譜
先験的制度尊重主義は現実の問題に有効か
先験的制度尊重主義は十分条件か必要条件か
比較アプローチは最善の答えに辿り着けるか
社会的選択理論の7つのメリット
第5章 不偏性と客観性
バークとウルストンクラフト
不偏性と客観性
グラムシと人類学的方法
孤独と正義
閉鎖的不偏性と開放的不偏性
第6章 閉鎖的不偏性の克服
外国と関わる理由
アダム・スミスは功利主義者か、ロールズの誤読
排他的無視(ネグレクト)とグローバルな正義
将来世代の利益
偏狭主義と地域の伝統
第Ⅱ部 推論の形
第7章 立場と幻想
リア王の立場
立場による客観性
客観的幻想
健康と客観的幻想
「喪われた女性」のインパクト
立場性と正義論
共感と立場に基づく限界の克服
私たちの隣人は誰か
第8章 合理性と他者
最大化問題が意味するもの
合理的選択と実際の選択
合理的選択理論は合理的か
主流派経済学の偏狭さ
アダム・スミスと共感
合理的な愚か者
コミットメント
コミットメントと目的
第9章 不偏的理由の複数性
「合理性」と「理に適うこと」の差
他者が拒否できないもの
拒否できないものの複数性
相互利益のための協力
契約論と相互利益
力を持つ者の義務
第10章 帰結主義と義務論
帰結主義者アルジュナと義務論者クリシュナ
最終的結果と包括的結果
帰結主義と実現
結果とその評価
第Ⅲ部 正義の材料
第11章 ケイパビリティとは何か
貧困と所得
貧困と自由
自由とアジア的価値
機会としての自由、過程における自由
ケイパビリティとは何か
ケイパビリティはアプローチである
ヌスバウムのケイパビリティのリスト
結果を超えて機会に進む
通約不可能性への恐怖
操作可能性の愚かしさ
自尊心の重要性
ケイパビリティ、グループ、コミュニティ
持続可能な開発、環境、ケイパビリティ
第12章 ケイパビリティ・アプローチのメリット
手段としての所得
貧困とケイパビリティの欠如
障がい者のケイパビリティ
女性と家庭内不平等
所得アプローチの問題点
第13章 幸福とケイパビリティ
憂鬱な科学
幸福と義務
ベンサムの真意
幸福の限界
幸福の証拠的役割
経済学の変容と社会的厚生関数
アローの不可能性定理
幸福と暮らしの良さ
苦痛と健康
福祉とケイパビリティ
第14章 平等と自由
何の平等か
ケイパビリティと平等
ケイパビリティと個人の自由
自由の多面性
ケイパビリティ、依存、干渉
パレート的リベラルの不可能性定理
ゲーム論で考える自由と結果
第Ⅳ部 公共的推論と民主主義
第15章 公共的理性としての民主主義
アジアの民主主義
民主主義と「討論による統治」
民主主義のグローバルな起源
イスラムの中の民主主義
報道とマスメディアの役割
第16章 民主主義の実践
ベンガル大飢饉
飢饉防止と民主主義
民主主義と経済発展
「人間の安全保障」と政治的な力
少数者の権利とインクルーシブな優先順位
第17章 人権とグローバルな義務
人権と日本国憲法
人権と法
自由としての権利
自由の「機会の側面」と「過程の側面」
完全義務と不完全義務
人権と利益
経済的社会的権利
人権として認められるプロセス
第18章 正義と世界
死にかけている人を見捨ててもいいのか
怒りと理性
正義が行われるのが見えること
理由の複数性
部分順序の有効性
比較の枠組み
開放的不偏性と他者の利害
グローバルな正義
正義論との共通点
あとがき
参考文献