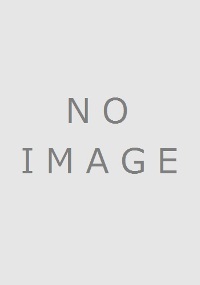法現象学入門
出版社: 法政大学出版局
- われわれの社会生活における法および法秩序は、いかにして現出しているのか。哲学と法学を架橋する体系的かつ包括的な決定的大著。
- われわれの社会生活における法および法秩序は、いかにして現出しているのか。哲学と法学を架橋する法現象学の理論枠組みを体系的に叙述する決定的大著。
- われわれの社会生活における法および法秩序は、いかにして現出しているのか。フッサールの影響下に法現象を論じた戦前の古典的法現象学を嚆矢とし、ハイデガー、シェーラー、メルロ=ポンティらの思考を継承した戦後法学の諸潮流を経て、現代の法現象学は人権、他者、責任、正義、自由といった問題圏へとその対象領域を展開している。哲学と法学を架橋する法現象学の理論枠組みを体系的に叙述する決定的大著。
- 日本語版への序文
序 言
第一部 導入──法現象学とは何か
第一章 法哲学の基本問題と法現象学の基本概念
第一節 法の本質と法概念
第二節 法の事実性と妥当性
第三節 自然法/理性法対実定法
第四節 法と道徳──法規範とその他の社会規範
第五節 法と正義
第六節 法と国家
第七節 法の諸機能──法と社会
第八節 法学─法哲学─法理論
第九節 思想史の発展と現在の議論──法現象学の位置
第二章 現象学の基本問題と法現象学の基本概念
第一節 事象そのものへ! 現象学的現象
第二節 実質的アプリオリ、本質直観と原本的直観(明証性)
第三節 還元と構成
第四節 超越論的主観性と超越論的間主観性、他者性
第五節 生活世界、内世界的現象学と超越論的現象学、現存在、実存
第三章 法現象学とは何でありうるか──諸々の問いかけや方向性、方法、時代にそった体系化の試み
第一節 体系化の試み(一)──法や法学との関係における(法)現象学
第二節 体系化の試み(二)──法現象学における法律家的、内世界的、形相的、超越論的な接近法
第三節 体系化の試み(三)──歴史的、方法的区分、テクストの選択
本書の構成について
第二部 法現象学の諸々の立場
予備的考察──エトムント・フッサールの現象学における法
第一節 法と還元
第二節 人格主義的態度における法の再獲得
第三節 法現象の現象学的特徴
第四節 社会存在論とモナド的目的論──愛の共同体
第五節 事実と形相の弁証法における法と国家
第六節 承認された法としての実定法(意志の共同体)──慣習道徳(Sitte)と区別される法、強制的規制(国家)としての法
第七節 国家と法、および理性法によるそれらの革新──目的論的で意志形成的な過程としての事実性と妥当性
第八節 現象学的理性法
第九節 結語──要約、展望、批判
第一章 古典的法現象学
第一節 形相的─実在論的法現象学──アドルフ・ライナッハ、エディット・シュタイン、ヴィルヘルム・シャップ、法のアプリオリな基礎づけと法存在論
第一項 アドルフ・ライナッハ「民法のアプリオリな基礎」(一九一三)
第二項 エディット・シュタイン『国家についての考察』(一九二五)
第三項 ヴィルヘルム・シャップ『法の新科学』第一巻『現象学的一研究』(一九三〇)
第二節 論理─実証主義的法現象学──ウイーン学派のフェリックス・カウフマン、フリッツ・シュライアー──ハンス・ケルゼンの影響下にあるアプリオリな法命題論と「現象学的実証主義」
第一項 エトムント・フッサールとハンス・ケルゼン──現象学的論理学と純粋法学
第二項 フェリックス・カウフマン『論理学と法学──純粋法学体系綱要』(一九二二)と『法の諸規準──法学的方法論の諸原理に関する一考察』(一九二四)
第三項 フリッツ・シュライアー『法の基本概念と基本形式──現象学に基づく形式的法理論と形式的国家論の構想』(一九二四)
第三節 生活世界的─社会存在論的法現象学
第一項 現象学的社会学、社会存在論、フッサールとケルゼンに繋がる法思考──アルフレート・シュッツと尾高朝雄
第二項 ゲルハルト・フッサール『法の力と法の妥当性』(一九二五)、『法と世界』(一九二九/六四)、『法と時間』(一九五五)
第二章 継承と新展開
第一節 ハイデガー、シェーラー、メルロ=ポンティと法現象学
第一項 ハイデガーと法現象学──ヴェルナー・マイホーファー『法と存在』(一九五四)
第二項 シェーラーと法現象学──エアハルト・デニンガー『法人格と連帯──特にマックス・シェーラーの社会理論に注目してなされる法治国家の現象学のための一考察』(一九六七)
第三項 メルロ=ポンティと法現象学──ウィリアム・ハムリック『法の実存的現象学──メルロ=ポンティ』(一九八七)
第二節 フランスにおける法現象学
第一項 ポール・アムスレク『現象学的方法と法理論』(一九六四)
第二項 シモーヌ・ゴヤール=ファーブル『法の現象学的批判に関する試論』(一九七〇/一九七二)
第三項 ジャン=ルイ・ガルディー『道徳と法の合理性についてのアプリオリな基礎』(一九七二)
第三節 人権の現象学──他者性、応答性、正義
第一項 ハンナ・アーレント──人権の現象学?
第二項 エマニュエル・レヴィナス──他者の人権
第三項 ジャック・デリダ──法、正義、脱構築
第四項 応答性、法学的意味での規範性と秩序──ベルンハルト・ヴァルデンフェルス、ペトラ・ゲーリング
第四節 自由と前所与性の間──さらなる法現象学の展望
第一項 ヘルベルト・シュピーゲルベルグ──実定法、慣習道徳法則、理念法
第二項 カルロス・コッシオ──自由と法現象学
第三項 実存主義的法理論
第四項 アロア・トローラー──前所与性と法現象学
第五項 法現象学の領域ないし周辺領域におけるその他の著作と潮流
第三章 法現象学──結論と展望
監訳者あとがき
参考文献
事項索引
人名索引